自動車の実験時代に生まれた異端児:1961年式シボレー・コルベア・ランプサイド


1960年代初頭――アメリカの自動車業界は、今では想像もつかないほどの“実験”に満ちていた時代でした。巨大なV8エンジンが市民の足として平然と使われ、未来的なフィン付きボディや航空機風デザインが流行し、ある種の「夢」と「挑戦」が道路を走っていた時代。そんな空気の中で、シボレーが放った異端のピックアップトラック――それが「コルベア・ランプサイド(Corvair Rampside)」です。
■ コルベアとは何だったのか?
「コルベア」と聞いてピンとくる人は、相当なアメ車通でしょう。1959年にGMのシボレーブランドから登場したコルベア(Corvair)は、当時のアメリカ車としては非常に珍しい構造を持っていました。空冷・水平対向6気筒エンジンをリアに搭載し、独立懸架のサスペンションを備えた軽量かつコンパクトな車体。これは、明らかにフォルクスワーゲン・ビートルの影響を色濃く受けたものであり、GMなりの「欧州小型車への対抗策」でもありました。


そんなコルベアには、乗用車だけでなく、商用車バリエーションも存在しました。なかでも一際異彩を放っていたのが、「ランプサイド」なのです。


■ ランプサイドの構造と特徴:側面から荷物が積める!?


ランプサイドは、コルベアの商用車派生型「グリーンブライア・バン(Greenbriar Van)」をベースにしたピックアップトラックで、驚くべき構造を持っていました。
最大の特徴はその名の通り、**“側面が開いてスロープになる”**という点です。通常のトラックは後方のテールゲートを開けて荷物を積み込みますが、ランプサイドでは右側側面が大きく開き、しかもそのパネルがスロープ状になって地面と繋がる構造になっていたのです。
● なぜそんな構造が可能だったのか?
これは、コルベアが「リアエンジン」であることに起因します。フロント側にはエンジンもトランスミッションもないため、床下スペースを極限まで下げることができたのです。その結果、中央床面はほぼ地面と同じ高さに設定でき、側面にランプ(スロープ)を設けるという構造が実現しました。
まるで現代の福祉車両やバイク用トランスポーターのような設計思想――この奇抜な発想は、まさに“時代の実験精神”そのものでした。
■ ランプサイドの兄弟「ロードサイド」との違い
ランプサイドには兄弟車が存在しました。それが「ロードサイド(Loadside)」です。


このロードサイドは、ランプの代わりに“平坦な荷台と床下収納”を備えた構造で、よりオーソドックスなピックアップトラックの使い勝手を意識して作られていました。つまり、
-
ランプサイド:側面スロープでバイクや荷物を積みやすい特化型
-
ロードサイド:一般的なフラットベッド型の使いやすさ重視
というコンセプト分けがされていたのです。
しかし、どちらも市場では苦戦を強いられることになります。
■ 販売面での失敗:市場が追いつかなかった革新
GMはコルベアシリーズを1960年から1964年まで販売しましたが、コルベアの商用車ラインナップにおいて、ピックアップ型は“ニッチ過ぎる存在”でした。
特にランプサイドは、そのユニークな構造が災いしてか、あまり売れませんでした。
-
ランプサイド:わずか17,786台
-
ロードサイド:たったの2,844台
一方で、バン仕様のグリーンブライアはそこそこ健闘しており、やはり商用車としては“普通の形”のほうが受け入れられやすかったという証左でもあります。


■ 参考:VWタイプ2ピックアップとの比較
このコルベア・ランプサイドの発想は、完全なオリジナルというわけではありません。先行して1950年代から存在したフォルクスワーゲンのタイプ2(通称:VWバス)には、既にピックアップ型やダブルキャブ、さらにはスロープ付きの商用仕様も存在していました。
実際、GMはVWの成功を受けてコルベアを企画したとも言われており、コルベアシリーズ自体が“アメリカ版VW”という文脈で生まれていたのです。
しかし、1964年に導入された「チキン・タリフ(Chicken Tax)」により、VWの商用車はアメリカ市場から姿を消します。これにより、国産のニッチトラックが再評価されるかと思いきや、コルベアトラックは既に販売終了しており、時代の波に乗れないまま終焉を迎えました。
■ リアエンジン車の限界とコルベアの終焉
コルベアは乗用車としても実は数々の試練に直面していました。1965年、弁護士ラルフ・ネーダーによる著書『Unsafe at Any Speed(どんな速度でも危険)』で、コルベアのリアサスペンション構造が問題視されたのです。
この事件が引き金となり、コルベアは“危険な車”というレッテルを貼られ、最終的に1969年に生産終了へと追い込まれました。つまり、商用バージョンのランプサイドやロードサイドの構造的ユニークさは、より広いユーザーには理解されることなく、消えていったのです。
■ 今なお愛されるクラシック:コレクターズアイテムとしての魅力
そんなランプサイドですが、現在ではクラシックカーとして一定の人気を誇ります。その奇抜なデザイン、リアエンジン×スロープという唯一無二のコンセプト、そしてアメリカ車とは思えないコンパクトな佇まい。コレクターやレストア好きにとっては“宝探し”の対象となっており、状態の良い個体はイベントでも注目を集めます。
近年では、ランプサイドをEV化して再生するプロジェクトなども登場しており、“未来的すぎた過去の車”として再評価されつつあります。
■ 結び:ランプサイドが遺したもの
1961年のシボレー・コルベア・ランプサイドは、商業的には失敗に終わりましたが、アメリカの自動車史において忘れてはならない存在です。なぜならそれは、
-
技術的にチャレンジングな構造
-
利便性への斬新なアプローチ
-
大量生産車で実現したユニークさ
といった、今では考えられないほどの“自由な発想”に基づいた車だったからです。
今、私たちがEVや自動運転、空飛ぶクルマの時代を迎えようとしている中で、かつての「ランプサイドのようなクレイジーな挑戦」が再び求められているのかもしれません。


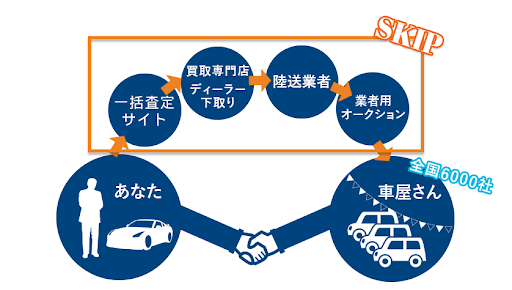




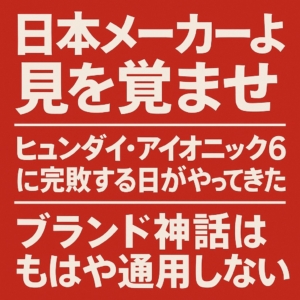



コメント