第1章:ホンダ・プレリュードの伝説と進化の歴史


ホンダ・プレリュードという名前には、かつての日本車が持っていた情熱と革新性が詰まっている。その誕生は1978年。当時、ホンダが国内外でブランドとしての確立を目指していた時代に、シビックとアコードに続く第3の乗用車ラインとして誕生したのがこの2ドアクーペ、プレリュードだった。
初代プレリュード(1978〜1982):静かなデビュー
初代プレリュードは、アコードのシャシーとエンジンをベースに開発されたが、よりスポーティで洗練されたクーペデザインを特徴としていた。全長4105mm、全幅1635mmというコンパクトなサイズながら、当時としては非常にモダンなスタイリングが話題となった。
しかし、性能面では控えめで、搭載された1.8L直列4気筒エンジンは最高出力72馬力と、現代基準でいえば大人しいスペックだった。それでも、「走る楽しさ」と「先進的なルックス」を追求した姿勢は、すでにプレリュードの“性格”を形成していた。
第2世代(1982〜1987):技術革新とデザインの洗練
1982年に登場した2代目プレリュードは、デザイン・性能ともに大幅に進化した。直線基調のスタイリングとポップアップ式ヘッドライトを採用し、当時の若者に圧倒的な人気を誇った。1.8Lおよび2.0Lエンジンが用意され、最高出力は110馬力まで向上。0-100km/h加速は約9秒となり、スポーティクーペとしての評価が一気に高まった。
また、このモデルからエアコンやパワーウィンドウなどの快適装備も充実し、実用性とプレミアム感の両立が図られた。
第3世代(1987〜1991):世界初の4WS搭載車
3代目プレリュードは、ホンダの技術力を世界に示すモデルとなった。最も象徴的なのが、世界初の量産車用「4WS(4輪操舵システム)」の搭載である。これにより、低速時には後輪が前輪と逆方向に、そして高速時には同方向に動くことで、卓越したコーナリング性能と取り回し性を実現した。
このモデルにはB20A型やB21A型といった新設計のエンジンが搭載され、最大出力は135〜150馬力にまで達し、VTECの登場前夜のプレリュードとしては完成度が高かった。
また、視界性を考慮したフラットなボンネット、低重心なボディ設計など、走行性能だけでなくドライバーとの一体感を意識した設計哲学も光っていた。
第4世代(1992〜1996):VTECの衝撃と現代的進化
プレリュードの歴史の中でも特に高い評価を得ているのが、この4代目モデルである。外観は丸みを帯びた有機的なデザインへと刷新され、全体的にモダンな印象へと変貌。ここで初めてホンダの名機「H22A型 DOHC VTEC」エンジンが搭載され、最高出力は190馬力、0-100km/h加速は6.7秒と飛躍的なパフォーマンスを誇った。
この時代のプレリュードは、単なる“若者向けクーペ”を超えて、マニア層にも訴求する本格的なスポーツクーペへと進化を遂げた。国内では「Si VTEC」や「SiR Sスペック」といったバリエーションが人気を博し、ホンダのVTECエンジン信仰を強固にした一因でもある。
第5世代(1997〜2001):ATTSの導入と静かな終焉
1997年に登場した5代目プレリュードは、性能的にも装備的にも集大成といえるモデルだった。H22Aエンジンは195馬力まで強化され、新たに「ATTS(アクティブ・トルク・トランスファー・システム)」という、フロントタイヤへのトルク配分を制御する先進技術が投入された。
このATTSは、後のアキュラSH-AWDの前身とも言われており、当時としては極めて先進的な制御システムだった。しかし、市場はすでにSUVやミニバンにシフトしており、スポーツクーペの需要は急速に縮小。北米を中心に人気があったプレリュードも販売台数が低迷し、2001年をもって生産終了となる。
“Prelude”という名前の意味
「前奏曲」という意味を持つ“Prelude”という車名は、まさにホンダの革新的な技術と走りの哲学の“序章”を象徴するものであった。実際に、プレリュードが採用した4WSやATTS、VTECといった数々の技術は、のちのシビックタイプR、S2000、アキュラNSXといったホンダスポーツの進化に繋がっている。
プレリュードは単なる過去の栄光ではない。むしろ、「技術で走りを面白くする」というホンダの姿勢を体現した存在であり、ホンダにとって“忘れられた名車”ではなく、“未来へつながる道標”なのだ。
第2章:なぜ今プレリュードを復活させるのか?


2023年ロサンゼルス・オートショーで公開された赤いプレリュードコンセプト。その瞬間、20年以上沈黙を保っていた伝説が再び動き出した。だが、多くの人が驚き、同時に疑問に思ったに違いない。「なぜ今、プレリュードなのか?」と。
この章では、ホンダがプレリュードを2026年モデルとして復活させるに至った背景と意図を多角的に掘り下げていく。
市場の再構築とスポーツカーの再評価


自動車市場はここ10年で大きく変化した。EVシフト、SUVブーム、自動運転技術の進化──。その一方で、「クルマを運転する楽しさ」という原点が見直され始めている。トヨタGR86やスバルBRZのヒット、マツダ・ロードスターの継続的な人気、日産フェアレディZの復活などはその証拠だ。
ホンダはその流れを見逃さなかった。かつてシビックやプレリュード、インテグラで一世を風靡したホンダは、今の時代にも「人とクルマの一体感」を再び提供できると信じている。そして、その答えがプレリュードだった。
シビックタイプRとNSXの間を埋める“第三のスポーツ”


ホンダの現在のスポーツラインアップは、FFベースの“Civic Type R”と、ミッドシップ+ハイブリッドAWDの“NSX”(2022年生産終了)という両極に分かれていた。その間を埋める手ごろなスポーツカーが存在していなかった。
2026年型プレリュードは、その空白を埋める存在だ。FFベースのハイブリッドパワートレイン、クーペスタイル、そして“走る楽しさ”をコンセプトに掲げたこのモデルは、まさにホンダスポーツの再編成における“第3の道”として設計されている。
ハイブリッド=退屈 の常識を覆す
ハイブリッドと聞くと「燃費は良いけど運転は退屈」と思う人は多い。しかしホンダはこの印象を覆すことに挑んでいる。
プレリュードに採用されると予想されているパワーユニットは、2.0L直列4気筒エンジン+デュアルモーターのe:HEVシステム。シビックハイブリッドなどにも採用されているこのシステムは、低回転域から強烈なトルクを発揮し、モーターによる静粛性とレスポンスを両立する。
特にS+モードと呼ばれるスポーツ制御が導入される見込みで、アクセルレスポンスやステアリングフィールが“ホンダ的”に調律されるという。
「4人乗り」の選択が示すもの
開発責任者の山上智之氏がオーストラリアのCarGuide誌の取材で語った言葉が印象的だ。
「これは、サーキットで全開走行するための“最速マシン”ではない。我々が目指すのは、“毎日乗れるスポーツカー”だ。」
この思想こそが、プレリュードの真のコンセプトを表している。つまり、GR86やBRZが“週末の楽しみ”であるのに対し、プレリュードは“日常に寄り添うパートナー”であるべきなのだ。その象徴が「2ドアながら4人乗れる」パッケージであり、実用性と趣味性の共存を狙った仕様である。
ブランドアイデンティティの再定義
ホンダは、電動化においても「ドライバーの感性に訴えること」を重要視している。無機質なEVではなく、走りを楽しめるハイブリッド。燃費や環境性能も大事だが、“乗って楽しいクルマ”を作るという姿勢は、ホンダファンにとってこれ以上ない朗報だろう。
プレリュードはまさにその象徴的存在であり、「ホンダがホンダらしくあるための指標」なのである。
このように、プレリュード復活は単なる“懐かしさ”ではない。市場の流れとホンダの理念が交差する地点において、論理的かつ戦略的に選ばれたモデルであり、その役割は単なる復刻車ではなく、未来に向けた“前奏曲”そのものである。
第3章:2026年型プレリュードのデザインと外観の魅力
2023年のロサンゼルス・オートショーで初披露されたコンセプトモデル──その鮮烈な赤いボディと、未来感を漂わせるデザインは、多くのホンダファン、そしてスポーツカーファンにとって衝撃的だった。2000年代初頭のスポーティな雰囲気とは異なり、2026年型プレリュードは「現代的で洗練された美」を前面に押し出した、新しいスタイルへと進化している。
では、デザインのどこにその“魅力”が宿っているのだろうか。
クーペらしさを貫くシルエット
まず注目したいのは、流れるようなルーフラインと低く構えたスタンスだ。Cピラーからリアエンドへと滑らかに下がるラインは、まさに“クーペ”の王道的美学を継承しており、空力を意識しつつも官能的なフォルムを描いている。
全高は低く抑えられており、視覚的なワイド感を強調。これにより、実際のサイズ以上に地面に吸い付くような重厚感を演出している。ホイールベースも長めに取られており、ショートオーバーハングと相まって、前後のバランスが取れたダイナミックなプロポーションを実現している。
新しさとホンダらしさの融合したフロントフェイス
フロント周りには、近年のホンダデザインの文脈が色濃く反映されている。細くシャープなLEDヘッドライト、グリルからバンパーへと滑らかに繋がる曲線美、そしてボンネット中央のラインが視線を車体の中心に集め、視覚的な統一感を生み出している。
また、開口部の大きなロアグリルは、冷却効率とスポーツ感を両立させる設計だ。機能美を追求しつつ、視覚的なアピールも抜群。今後の市販モデルでは多少デザインが簡略化される可能性もあるが、ホンダがこのデザインを“プレリュードらしさ”として維持しようとしていることは間違いない。
リアエンドの造形:力強さと未来感
リアセクションのデザインも、非常に完成度が高い。テールランプは一文字型のLEDバーで構成され、現代的な“EV的イメージ”を想起させる。中央には大きく“PRELUDE”のロゴが配置され、ブランド力を主張している。
トランクフードの先端にはさりげないスポイラーが一体化されており、空力性能を高めるだけでなく、走行時の安定性にも貢献する。全体として、力強くもスタイリッシュなリアビューは、まさに“走りのためのデザイン”というホンダの姿勢を象徴している。
カラーリングとディテールの妙
コンセプトカーでは鮮やかな赤(プレミアム・レッド・パールに近い)を採用していたが、市販モデルではホンダ伝統の「チャンピオンシップホワイト」「モダンスチール」「オブシダンブルー」などが展開されると予想されている。
また、細部にはブラックアウトされたピラーやミラー、エアロパーツが散りばめられており、スポーティさと高級感が両立されている。20インチ近いホイールは立体感のあるデザインで、現代のスポーツクーペにふさわしい足元を演出している。
競合車と比較しても引けを取らない
トヨタGR86やスバルBRZ、日産フェアレディZといった国産スポーツクーペの中でも、プレリュードは外観の完成度において決して劣らない。特に、ホンダならではの“機能と美の融合”という設計思想が全体に反映されており、他メーカーのスポーツクーペとは一線を画す。
むしろ、NSXの流れをくむデザインの要素が見え隠れしており、FFスポーツでありながら“特別感”を放っていることが、ファンの心を掴む要素となっている。
総じて、2026年型プレリュードは、単なる“復刻版”ではない。「懐かしさ」と「革新性」のバランスを見事に取ったそのデザインは、未来のホンダスポーツカー像を示す先駆けとなりうる存在だ。
第4章:ハイブリッドパワートレインと予想される走行性能
2026年型プレリュードが復活するという報せの中で、最も賛否を呼んだのが「ハイブリッド」というキーワードだった。ホンダファンやスポーツカーファンの間では、「プレリュードにハイブリッドなんて邪道だ」という声もあれば、「今の時代にこそ必要な進化だ」と受け止める意見もある。
しかし、ホンダは決して“妥協”でこの選択をしたわけではない。むしろ、「走る喜び」を未来にも継承するために、あえてハイブリッドという技術を選び抜いたのだ。
2.0L直列4気筒+デュアルモーターのe:HEV
プレリュードに搭載されると予想されているのは、ホンダがシビックハイブリッドやCR-Vハイブリッドなどに採用している**e:HEV(イー・エイチ・イーブイ)**システム。これは、2.0リッターの直列4気筒エンジンに2つの電動モーターを組み合わせた自己充電式ハイブリッドシステムである。
このシステムでは、基本的にモーターが駆動を担い、エンジンは発電専用として機能する。必要に応じてエンジン直結の走行モードにも切り替わる。これにより、モーターのトルクフルでスムーズな加速と、エンジンによる航続距離の長さを両立することができる。
現行のシビックハイブリッドでは、最高出力204馬力、最大トルク232 lb-ft(約315Nm)を発揮しており、プレリュードもほぼ同等のスペックになると予想されている。
CVTではなく電動駆動ユニットによるレスポンス
e:HEVは「CVT車」と誤解されがちだが、実際には無段階の電動駆動ユニットによるシステムで、トルクコンバーターも変速機も存在しない。そのため、従来のガソリン車に比べて加速の“つながり”が極めて自然であり、ワンテンポ遅れるといったネガティブな印象も少ない。
特に市街地走行では、発進からすぐにトルクが立ち上がるため、電動車特有の「瞬発力」が楽しめる。これは従来のプレリュードとはまったく異なる、新しい“スポーツ感”だ。
S+モードによるドライバーエンゲージメント
ホンダは、2026年型プレリュードに「S+(スポーツプラス)モード」を搭載するとしており、このモードではステアリング、アクセルレスポンス、サスペンション(電子制御がある場合)などが一括でスポーティに変化する。
このS+モードの重要な点は、「ただ速くなる」のではなく、「運転していて気持ちいいと感じられる」ことを目指している点にある。単にタイムを縮めるための装置ではなく、ホンダが提唱する“人馬一体”のドライビングフィールをサポートするシステムなのだ。
駆動方式はFFが有力、AWDの可能性も?
歴代プレリュードはすべて前輪駆動(FF)であり、今回も基本はFFになると予想される。しかし、電動モーターを使ったe-AWDの可能性も完全には否定できない。
例えば、後輪に小型モーターを追加することで電動4WDとする手法は、トヨタのE-Fourや日産e-4ORCEのように近年のハイブリッドカーで一般的になりつつある。
現時点ではプレリュードのAWD仕様に関する情報は未確認だが、今後スポーツ性の高い「タイプS」や「プレリュードSi」的なバリエーションが登場すれば、その際に採用される可能性もある。
0-100km/h加速と予想パフォーマンス
現行シビックe:HEVが約7.5秒で0-100km/h加速をこなすことから、軽量かつ空力に優れるクーペボディのプレリュードでは約7秒前後になると予測されている。
これはGR86(6.3秒)やBRZ(6.5秒)には届かないが、街乗りとワインディングを楽しむには十分な速さであり、なにより電動モーターの即応性によって体感加速はより鋭く感じられるだろう。
第5章:4人乗りという選択と使い勝手の進化
スポーツカーにおいて、「何人乗れるか?」は本来、最優先されるべきではない。しかし、日常使いの実用性とスポーツ性のバランスを取るためには、この“座席数”という要素がじつは非常に重要な意味を持つ。2026年型ホンダ・プレリュードは、そのバランスに真剣に向き合ったクルマだ。
2ドア+4シーターのパッケージング
新型プレリュードは、トヨタGR86やスバルBRZと同様、2ドアながら後部座席を備える4人乗りとして開発されている。これは「日常使いもできるスポーツカー」というホンダの基本思想に基づいた設計であり、スポーツカーが“週末のオモチャ”で終わらないための工夫とも言える。
当然、リアシートのスペースは限られる。大人が長時間快適に過ごせるほど広くはないが、短距離の移動や子ども、小柄な乗員であれば十分に活用できるレベルだと予想されている。
実用性を高める後席装備
開発責任者である山上智之氏は、「日常使いを重視した」と明言しており、その言葉通り、新型プレリュードではリアシートにもUSBポートやエアコン吹き出し口が装備される可能性がある。また、シートバックのリクライニング角度や乗降性にも配慮がなされると見られている。
ホンダはミニバンやSUVで培った“空間設計”のノウハウがあるだけに、この2+2パッケージでも最大限の快適性を確保してくる可能性が高い。
トランク容量とシートアレンジ
プレリュードはクーペでありながらも、ある程度の積載性を持たせることが予想される。例えば、リアシートの6:4分割可倒式や、トランクスルー機能の採用により、長尺物の収納も可能になるかもしれない。
旅行や趣味、スポーツギアの収納など、従来の“使いにくいスポーツカー”とは一線を画す実用性を持たせることは、ホンダが目指す「毎日使えるスポーツ」の理念にも合致する。
デートカーから“家庭持ちスポーツ”へ
かつてのプレリュードは“デートカー”として一世を風靡した。しかし現代では、その役割はより多様化している。家庭を持ったホンダファンや、子育てと趣味の両立を望むユーザーにとって、2ドアであっても4人乗れるという事実は非常に魅力的だ。
例えば、週末は家族でショッピングに、平日はワインディングで気分転換に走る──そんな二面性のあるクルマとしてプレリュードが蘇るのだ。
女性ユーザー・若年層にも届くデザインと機能
2ドアというと男性的なイメージが強いが、新型プレリュードは流線的な美しさと現代的な装備を兼ね備えており、女性ユーザーにも訴求力がある。また、ハイブリッドによる低燃費・静粛性は、スポーツカーに憧れながらも「維持費が…」と二の足を踏んでいた若年層にも優しい設計となっている。
これまで「実用性を取るならSUV、楽しさを取るなら2シーター」と二極化されていた選択肢の中に、“ちょうどいい”スポーツクーペとしてプレリュードは割って入ってくる。4人乗りという設計は、その“ちょうどよさ”を象徴するポイントなのだ。
第6章:インテリアと先進機能──Civic/Integraとの共通点
プレリュードという車名には、外観の美しさや走行性能だけでなく、「乗る喜び」──すなわちインテリアでの体験にも期待が集まる。2026年モデルでは、ホンダの最新世代モデルであるCivicやIntegraの流れを組みつつも、独自の“プレミアム・スポーツ”な空間づくりがなされているようだ。
この章では、新型プレリュードの内装に関する特徴と、装備、そして先進的なテクノロジーについて詳しく見ていく。
インテリアデザイン:直線と曲線の調和
インテリアデザインは、現行シビックやインテグラに見られる水平基調のインパネ構成をベースにしており、ダッシュボード中央には蜂の巣状のエアコンベントと金属調のアクセントが配され、質感と機能性を両立している。
また、プレリュードではクーペ専用として、より低い着座位置やスポーティなバケットシート風のシート形状が採用されると予測されている。カラーリングもブラック×ボルドーやグレー×ネイビーなど、若干の高級感を感じさせるコンビネーションが導入される可能性が高い。
メーターとディスプレイ類
メーターパネルは10.2インチのフルデジタル液晶ディスプレイが予想され、S+モード時にはスポーツ表示に切り替わる演出も組み込まれるだろう。中央には9インチ以上のインフォテインメントタッチスクリーンを備え、Apple CarPlay・Android Autoのワイヤレス対応も標準装備とされる見込みだ。
さらに、CivicやAccordで採用されている**Googleビルトイン機能(Googleマップやアシスタントとの連携)**の搭載も噂されており、よりスマートなカーライフが期待できる。
シートと快適装備
前席はホールド性に優れたスポーツシートが採用され、Sグレード以上ではシートヒーター/ベンチレーションや、パワーシート機能が搭載されると見られている。リアシートはやや簡素だが、ドリンクホルダーやUSB-Cポートの追加などで実用性は十分に確保される見込みだ。
また、静粛性向上のためのアクティブノイズキャンセリング技術の採用も考えられており、ハイブリッドの静粛性と相まって、上質な移動空間を演出する。
Honda Sensingと運転支援技術
新型プレリュードにも当然ながらHonda Sensingが標準装備される。これは以下のような先進運転支援機能を統合したホンダの安全パッケージだ。
-
衝突軽減ブレーキ(CMBS)
-
道路逸脱抑制機能(RDM)
-
アダプティブクルーズコントロール(ACC)
-
LKAS(車線維持支援システム)
-
ブラインドスポットモニター(BSI)
これらの装備により、「スポーツカーは危険・不安定」といったイメージを覆し、誰でも安心して乗れるスポーツカーという地位を確立しようとしている。
ボタンとUIは“直感的に”
近年、各社が物理ボタンを廃止してタッチ操作に移行する中、ホンダはあえて物理ノブやスイッチの残存を選んでいる。エアコンやオーディオボリュームなど、運転中に触れることが多い機能については物理操作を維持し、“直感的な使いやすさ”を追求しているのもホンダらしさだ。
全体として、プレリュードのインテリアは「最新の機能性」と「クーペとしての包まれ感」、そして「誰でも扱える安心感」が絶妙なバランスで融合しており、**まさに“現代のスポーツカーの理想形”**と言える空間に仕上がることだろう。
第7章:競合モデルとの比較(GR86、Z、シビックタイプRなど)
2026年型ホンダ・プレリュードが目指す市場には、すでに多くの名だたるライバルが存在している。では、プレリュードはその中でどのような立ち位置を取るのか? ここでは、主要な競合モデルとスペック、思想、価格、パフォーマンスを比較しながら、プレリュードの独自性と“勝ち筋”を明らかにしていこう。
主要競合モデルと概要
以下は、プレリュードと同価格帯・同ジャンルとされる主要競合のリストである。
| 車名 | 駆動方式 | エンジン | 出力 | 価格(USD) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ホンダ・プレリュード(予想) | FF | 2.0L ハイブリッド | 204ps | $31,000〜38,000 | S+モード搭載 |
| トヨタ GR86 | FR | 2.4L NA | 228ps | $29,000〜34,000 | 6MTあり |
| スバル BRZ | FR | 2.4L NA | 228ps | $30,000前後 | GR86と兄弟車 |
| 日産 フェアレディZ | FR | 3.0L V6ターボ | 405ps | $42,000〜53,000 | 完全ハイパワー |
| ホンダ シビックタイプR | FF | 2.0L ターボ | 315ps | $44,000前後 | サーキット志向 |
価格とポジショニングの絶妙なバランス
GR86やBRZと比較すると、プレリュードは価格でわずかに上回る可能性が高いが、その分ハイブリッドシステムによる低燃費・静粛性・装備の充実が際立つ。
また、フェアレディZやシビックタイプRのようなハイパフォーマンスモデルよりは抑えた価格帯で、日常性と走行性をバランスさせた「中間的存在」としてのポジションを明確にしている。
これは、若年層からリターン層まで幅広い層をターゲットにできるという利点でもある。
駆動方式の違いが示す“キャラクター”
-
GR86/BRZは「FRの楽しさ」
-
Zは「パワー重視のラグジュアリーFR」
-
シビックタイプRは「FF最速」
-
プレリュードは「FF+電動の滑らかさと実用性」
FF=つまらないという声も一部にあるが、プレリュードはその固定観念を覆す。e:HEVによるトルクフルな低速加速と、前輪駆動ならではの扱いやすさは、**日常での“速さと安心感”**を提供する。
また、雪道での安定性や維持費(タイヤ・駆動系部品など)においてもFFは実用的だ。
性能だけでなく“使い勝手”でも優位性
GR86やBRZ、Zなどはリアシートがあるとはいえ、実質2シーターに近い。一方、プレリュードは4人乗りが可能で、リアシートにも最低限の居住性があることがポイント。
さらに、インフォテインメント機能、安全装備(Honda Sensing)、燃費性能など、“暮らしの中での便利さ”においてプレリュードは圧倒的に優れている。
走行性能 vs 体験価値
フェアレディZやシビックタイプRは、確かに速い。しかし、プレリュードは速さを競うのではなく、「いかに気持ちよく走れるか」を重視して開発されている。これが、“楽しい≠速い”という新しいスポーツカーの価値観を提示している点であり、従来の“スペック至上主義”とは一線を画す。
ライバル不在の“隙間”を埋める1台
結果として、プレリュードはGR86よりもプレミアムに、タイプRよりも穏やかに、Zよりも現実的に──という、いずれのライバルとも直接ぶつからない絶妙なポジションを築いている。
これはホンダが「売れるスポーツカーではなく、“選ばれる”スポーツカーを作る」ことを目指している証だ。
第8章:スポーツ性はどこまで継承されるのか?
プレリュードと聞けば、多くのホンダファンは「スポーツクーペ」「走りの楽しさ」「VTECの高回転サウンド」などを思い浮かべるだろう。では、2026年に復活する新型プレリュードは、そうした過去の“スポーツ性”を本当に継承しているのか──あるいはまったく新しい“走り”を提案する存在なのだろうか?
この章では、スポーツ性という観点から新型プレリュードを分析していく。
「最速」を狙っていない明確なメッセージ
プレリュードの開発責任者・山上智之氏は、「このクルマはサーキットでタイムを削るためのモデルではない」と明言している。つまり、シビックタイプRのようなサーキット志向のホットハッチとは一線を画す存在だ。
これは一見すると“スポーツ性の放棄”のように聞こえるが、実際はまったく逆である。「あらゆるシーンで気持ちよく走れる」こと──すなわち、走行性能を“数字”ではなく“体験”として捉え直している点が新型プレリュードの大きな特徴なのだ。
e:HEVがもたらす電動スポーツの新境地
先述の通り、プレリュードは2.0Lエンジンとデュアルモーターによるハイブリッドシステムを採用する。加速の瞬発力、レスポンス、静粛性という点では、従来のガソリン車よりも優れている点も多い。
例えばワインディングを走るとき、アクセルを踏み込んだ瞬間にモーターが即座にトルクを発生させることで、コーナー脱出時の加速は非常にスムーズかつ鋭い。この特性は、VTECエンジンとは違った形で「走りの一体感」を提供してくれる。
S+モードによるドライバー主体の制御
ドライブモードに搭載される予定の「S+モード」では、アクセルレスポンス、ステアリングの重さ、パワートレインの出力制御がよりスポーティに切り替わる。
これは単なる演出ではなく、ドライバーが「今、この瞬間に走りを楽しみたい」と思った時に、それに応えてくれる応答性を提供するための機能だ。つまり、“意思に即応するスポーツ性”──これが新型プレリュードの本質である。
車体設計とサスペンションセッティング
プレリュードのボディは、現行のシビックやインテグラと共有される可能性が高い「Honda Architecture」をベースにしている。このプラットフォームは、剛性・重量バランス・サスペンション自由度において極めて優秀であり、Civic Type Rもこの構造を基にしている。
そのため、たとえFFであっても「曲がる楽しさ」「ラインをトレースする快感」を味わえるシャシーとなる可能性は高い。特にサスペンションセッティングでは、街乗りでの快適性とスポーツ走行時の引き締まった挙動が両立されるよう、電子制御ダンパーや可変ステアリングの搭載も検討されている。
音と感性の演出
「スポーツカーらしい音」がないという懸念に対し、ホンダは人工エンジンサウンドの導入を示唆している。これはスピーカーを通じて“加速感”に応じた音を車内に届ける仕組みで、ドライバーの感性を刺激するための演出だ。
もちろん、嘘くさい演出は逆効果になるリスクもあるが、ホンダはS2000やNSXで培ってきた“音の演出”にもこだわりを持つメーカーであり、そのあたりの調律は期待してよいだろう。
“楽しさ”の定義を変えるプレリュード
結局のところ、2026年型プレリュードは「速いかどうか」ではなく、「楽しいかどうか」で勝負している。スペックや馬力を競うのではなく、ドライバーの意思に応えてくれるフィーリング、毎日乗りたくなる快適さ、そして日常と非日常の両立──そうした**“現代的スポーツ性”の再定義**こそが、この新しいプレリュードに託された使命なのだ。
第9章:価格帯と市場投入時期、誰が買うのか?
新型プレリュードの魅力は、そのデザインや走りだけにとどまらない。「いくらで買えるのか?」「いつ手に入るのか?」「どんな人に向いているのか?」──この章では、プレリュードの価格設定と発売時期、ターゲットとなる顧客層について徹底的に掘り下げていく。
価格帯:$31,000〜$38,000の現実的なスポーツクーペ
ホンダはまだ正式な価格を発表していないが、米国市場での予想価格は**約$31,000〜38,000(日本円で約450万〜550万円)**になるとされている。これはシビックハイブリッドの上位グレードと重なりつつも、タイプRやNSXよりは手の届く価格帯だ。
この価格設定は、GR86やBRZのエントリーグレードより高めだが、ハイブリッドシステム・安全装備・快適性・質感を加味すれば妥当、あるいは割安と評価される可能性がある。
また、上位グレードにオプションで電子制御サスペンションや大型ナビ、プレミアムオーディオなどを組み込むことで、価格は$40,000台に乗る場合もあるが、それでもプレミアムスポーツカーとしては十分に現実的だ。
発売時期:2025年末から2026年初頭が有力
ホンダは「2026年モデル」としてプレリュードをリリースする予定であり、2025年の年末ごろから北米市場を皮切りに発売開始されると見られている。日本市場への導入は北米から数ヶ月遅れる可能性があるが、2026年春〜夏には国内でも正式販売がスタートする見込みだ。
ディーラー向け資料や事前予約は、2025年秋ごろから展開されると予想される。
購入層①:かつてプレリュードを愛した“リターン層”
一番わかりやすいターゲットは、かつて80〜90年代にプレリュードに憧れ、あるいは実際に所有していた層だ。彼らは現在40代〜50代に差し掛かっており、家族を持ち、ある程度の経済的余裕があり、しかし再び“自分のためのクルマ”を探しているタイミングでもある。
こうした層にとって、スポーティだが過激すぎない、日常性も備えたプレリュードはまさに“待ち望んでいた1台”となるだろう。
購入層②:環境性能も大事にする若年層
ハイブリッドパワートレインと先進装備を備えたプレリュードは、20代後半〜30代前半の若年スポーツ志向ユーザーにもアピールする。
燃費・維持費・車内快適性を重視しながらも、“かっこよくて楽しいクルマ”を求める層にとって、プレリュードはGT-RやフェアレディZのような「高嶺の花」ではなく、“背伸びすれば手が届く”憧れの存在として位置付けられる。
購入層③:ミニバンやSUVに飽きたファミリーユーザー
子育てが一段落し、ミニバンやSUVから「もう一度クルマを楽しみたい」と考える層にもプレリュードは響く。2ドアながら4人乗れる構造と、意外な実用性は**“家族持ちでも無理せず乗れるスポーツクーペ”**として、新たなライフスタイル提案にもつながる。
週末のドライブだけでなく、通勤、買い物、ちょっとしたお出かけまで、“使えるスポーツカー”として活躍することだろう。
プレリュードを選ぶという選択
速さを求めるならタイプR、個性を求めるならZ、手軽さを求めるならGR86。それらとは異なる軸で、**「楽しさと現実のちょうど中間」**を選ぶなら、プレリュードという選択は極めて理にかなっている。
クルマが“ただの移動手段”から“感情を揺さぶる存在”へと戻りつつある今、プレリュードは**“賢い感性派”のためのスポーツカー**として確かな地位を築く可能性がある。
第10章:プレリュード復活の意味──ホンダのブランド戦略としての位置づけ
2026年、ホンダが“プレリュード”という名前を再び世に放つ──その事実だけで、多くのファンは熱狂し、驚き、そして疑問も抱いた。なぜ今、プレリュードなのか? なぜハイブリッドなのか? NSXやタイプRとはどう違うのか?
この章では、ホンダがプレリュードという車名を現代に蘇らせた意味、そしてそれがブランド全体においてどのような役割を担うのかを読み解いていく。
プレリュード=前奏曲。その本来の役割
“Prelude”とは音楽用語で「前奏曲」を意味する。その名の通り、1978年に登場した初代プレリュードは、ホンダが“走り”や“個性”を追求する姿勢の前兆とも言える存在だった。
そして今回、再びプレリュードの名が与えられたモデルは、ホンダの未来のスポーツカー戦略を象徴する前奏曲となるべく設計されている。これは偶然でも懐古でもない。ホンダの“これから”を提示するモデルとして、プレリュードは再びステージに上がるのだ。
電動化とスポーツの融合
近年のホンダは、EV専用モデルの「プロローグ(Prologue)」や「0シリーズ(ゼロシリーズ)」など、電動化に向けたラインアップを本格化させている。しかし、いきなり“完全なEV”ではなく、段階的にハイブリッドを通して移行する戦略を取っているのがホンダの特徴だ。
プレリュードはその橋渡し的存在として、**“電動化の中でも走る楽しさを忘れないモデル”**として開発されている。これは、他社のスポーツモデルがEV化に苦しむ中で、ホンダが選んだ現実的かつ感性的な答えだ。
タイプRとNSXを繋ぐ“第三の柱”
ホンダのスポーツブランドは、長らく「タイプR」と「NSX」という二極構造だった。タイプRはFFを極めた“戦闘的マシン”、NSXは先進技術とブランド価値を象徴する“ハイエンドスポーツ”。
その中間に、価格・性能・使い勝手・デザインすべてを“ちょうど良く”収めたスポーツモデルが存在していなかった。プレリュードは、まさにその隙間を埋める**“第3の柱”**となる。
プレリュードが担うグローバル戦略
プレリュードは単なる国内市場向けの懐古モデルではなく、北米・欧州・アジアすべてに共通して訴求できるスポーツクーペとして設計されている。これはホンダが世界中のユーザーに対して「私たちは今も“走り”を重視している」と示すメッセージでもある。
特に、燃費・排ガス規制が厳しい欧州市場において、ハイブリッドのスポーツクーペは貴重な存在であり、環境対応型スポーツという新しい市場セグメントを狙っている可能性も高い。
“ホンダらしさ”を取り戻す象徴
ここ数年、ホンダはSUV化・電動化を進める中で、「ホンダらしさが薄れた」と言われることもあった。かつては“エンジン屋”として名を馳せ、モータースポーツでの勝利と市販車へのフィードバックがブランドの核だったはずだ。
プレリュードの復活は、そうしたファンの期待に対する**“ホンダの自己肯定的な回答”**でもある。「私たちは、今も楽しいクルマを作りたい。乗ることが喜びであるクルマを」と。
それを、過去の遺産をなぞるのではなく、**“未来の技術と感性で作り直す”**という形で提示した──それが、プレリュード復活の真意なのだ。


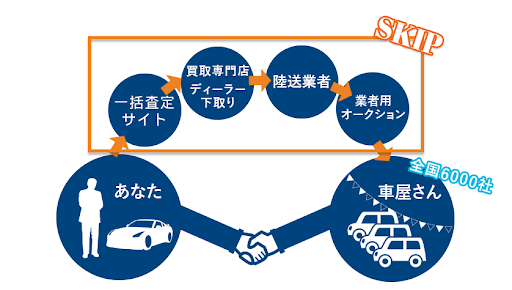








コメント