
はじめに:日産はなぜ「関税」をチャンスと見るのか?
2025年春、ニューヨーク国際オートショーで注目を集めたのは新型車だけではありませんでした。日産米国法人の幹部2名、ヴィナイ・シャハニ(営業・マーケティング責任者)氏とポンズ・パンディクティラ(商品企画責任者)氏が、米国メディアのインタビューで明かした戦略が話題を呼んでいます。
現在、トランプ政権の復帰により米国では25%の輸入関税が再び導入され、外国車メーカーにとっては打撃とも言える状況。しかし、日産はこの危機的状況を「追い風」と捉えているのです。
なぜ日産は“関税”を「ゴールデン・オポチュニティ(千載一遇の好機)」と考えるのでしょうか?この記事では、両氏の発言を軸に日産の現在地と未来戦略、さらには日本市場とのつながりまでを徹底解説していきます。
米国生産体制が日産の“盾”に
スマーナ工場とキャントン工場の存在
日産は1983年から米国テネシー州スマーナでの現地生産を開始しており、現在では以下の主力モデルを製造しています:
-
日産ローグ(Rogue)
-
パスファインダー(Pathfinder)
-
ムラーノ(Murano)
-
インフィニティQX60
また、ミシシッピ州キャントン工場では以下を生産:
-
フロンティア(Frontier)
-
アルティマ(Altima)
関税が課されるのは「輸入車」であるため、これら米国内生産の車種は価格競争力を維持できます。この点が、他の輸入依存度が高いメーカーとの明確な差となるのです。
メキシコ工場と日本製モデルの位置づけ
一方で、ヴァーサ(Versa)、セントラ(Sentra)、キックス(Kicks)などの小型モデルはメキシコ製、アルマーダ(Armada)やフェアレディZ(Z)は日本からの輸入です。
輸入車への関税圧力が高まる中で、日産は米国内生産モデルをさらに強化し、戦略的に輸入モデルの位置づけも再構築しています。
新型ローグの鍵は「ハイブリッド化」
ハイブリッド+PHEV展開の強化
シャハニ氏は「ローグの生産を日本から米国にさらに移行する」と明言。そして次世代ローグにはついに待望の「ハイブリッド」および「プラグインハイブリッド(PHEV)」モデルが登場予定です。
米国では依然としてガソリン車需要が根強いものの、低燃費・低価格のモデルに対する関心は高く、日産のローグはその需要の“ど真ん中”に位置します。
新型ローグが関税を回避した価格で、なおかつ燃費性能でも優れていれば、これは他社に対する大きなアドバンテージとなるでしょう。
売れ筋小型車の強さと進化
キックスのリブランディングと価格戦略
パンディクティラ氏は「新型キックスは前モデルとは完全に別物。価格はほぼ据え置き」と語ります。
-
価格帯:21,000ドル~28,000ドル
-
デザイン刷新
-
内装・安全性強化
この「価格据え置きで内容を一新する戦略」は、インフレと関税のダブルパンチで苦しむ米国市場において、日産が取るべき“正攻法”なのです。
セントラの次期型も視野に
セントラは現在モデル末期ながら高い販売を維持しており、2026年には新型が登場予定です。ここにもハイブリッドやEVの可能性があり、ローグとともに日産の基盤を支える柱となるでしょう。
日産の「30,000ドル以下戦略」とは?
手頃な価格帯でのフルラインナップ
シャハニ氏が強調したのは「30,000ドル以下の車を6車種揃える」という点。これは現代の米国市場では非常にレアなことです。
実際にこの価格帯に収まる日産車は:
-
ヴァーサ
-
セントラ
-
キックス
-
ローグ(下位グレード)
-
アルティマ(下位グレード)
-
フロンティア(2WDモデル)
多くの自動車メーカーが“高価格志向”にシフトする中、日産は「手の届くブランド」を自認し、このレンジでの勝負に力を入れています。
「原点回帰」への想いと未来への期待
“ダイヤの原石”を見直す
「私たちは一時期、ブランドの“モジョ(魅力)”を失ってしまった」と語るシャハニ氏。日産はかつて“反骨精神あふれる日本ブランド”として支持されてきました。
今こそ、その“らしさ”を取り戻すとき。派手なハイエンドモデルではなく、地に足のついた製品力と価格設定こそが、日産の原点であり武器です。
復活の鍵となる2つの提案:「Xterra」と「GT-R」
待望の新型エクステラ(Xterra)
Xterraはかつて米国で人気を博した本格SUV。今また、アウトドア志向の高まりと共に“復活希望”の声が多く寄せられています。
パンディクティラ氏も「なんとしても出したい」と熱く語っており、EVやハイブリッドとして再登場する可能性が高まっています。
次期GT-Rへの期待
そしてもう一つが、日産の象徴であるGT-R。EV時代におけるスポーツカー像が問われる中で、日産の技術力とブランド力を再認識させる重要な存在です。
シャハニ氏も「私も出したい」と語るGT-Rは、復活の“象徴”となり得ます。
LEAFの進化:クロスオーバーEVとしての再出発
LEAFは世界初の量産EVとして一時代を築きましたが、今や競争は熾烈。そこで日産は新型LEAFを「コンパクトEVクロスオーバー」として再設計中です。
SUVスタイルと利便性、そして価格を武器に、再び量販EV市場の覇権を狙います。
歴史は繰り返すか?1970年代の再来
1973年のオイルショックをきっかけに、ダットサン(現在の日産)は高燃費・コンパクト車でアメリカ市場を席巻しました。大型で燃費の悪いアメ車が苦境に陥る中、日本車が台頭したのです。
2025年の関税危機も、ある意味でそれに近い状況。低価格で燃費に優れた車種を揃える日産は、再び“下剋上”を果たすポテンシャルを秘めています。
まとめ:日産は本当に“復活”するのか?
日産が関税危機を「ゴールデンチャンス」と捉える理由は明確です:
-
米国内に強固な生産拠点を保有
-
低価格帯に強い商品力
-
ハイブリッドやEVなど次世代モデルへの備え
-
ブランドとしての原点回帰
ただし課題も少なくありません。ブランディング戦略の再構築、マーケティング強化、そしてGT-RやXterraなど“夢”のある商品をいかに実現するかが鍵となります。
日本の消費者にとっても、これは他人事ではありません。国内市場でも求められるのは「身の丈に合った価格と、しっかりした商品力」。日産の米国での挑戦は、やがて日本にも還元されるでしょう。
かつてのように、日産が「面白いクルマをつくるブランド」として再評価される日を、私たちも待ち望みたいと思います。


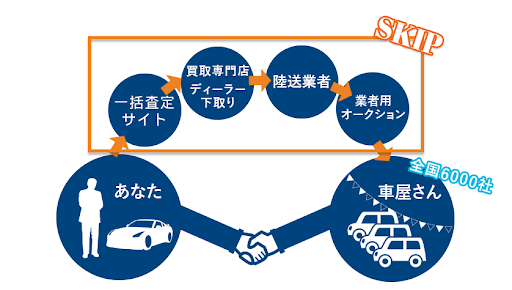








コメント