EV戦略の転換点:ホンダが大型電動SUVを開発中止、見えてきた次世代モビリティの現実
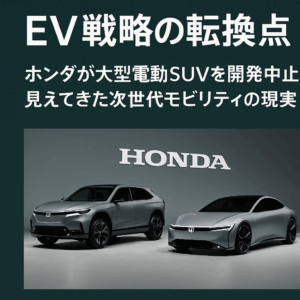
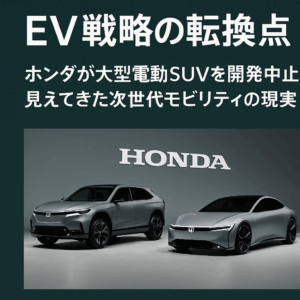
2025年、自動車業界はかつてないほどの混迷の時代に突入している。2030年を目標に「脱内燃機関」を掲げ、電動化へ突き進んでいた各社の戦略が、ここにきて大きく見直されはじめた。EV(電気自動車)の普及が急ブレーキをかけ、消費者の支持も足踏み。さらには、地政学的リスクや中国勢の猛攻により、各メーカーの「EV至上主義」は現実の壁に直面しつつある。
その象徴的なニュースが、ホンダによる大型EV SUVの開発中止だ。2027年に北米市場投入を予定していたホンダのフラッグシップEV計画は、わずか数年で棚上げとなり、EVへの巨額投資も大幅に削減される見通しとなった。
この出来事は、ホンダ一社だけの方針転換にとどまらない。ポルシェ、ロータス、ミニ、日産、ボルボ、さらにはメルセデスやBMWといった欧州勢までもが、EV一辺倒からハイブリッドや内燃機関の再評価へと舵を切り始めている。
本記事では、ホンダの開発中止の背景を軸に、今なぜEVの流れが鈍化し、内燃機関やハイブリッドが再評価されているのか、そして中国EV勢との熾烈な競争と欧米日メーカーの生き残り戦略を、2万字にわたって徹底的に掘り下げていく。
第1章:ホンダのEV戦略に起きた劇的な変化
ホンダが2025年7月に発表した内容によると、2027年に北米市場投入を予定していた大型EV SUVの開発中止を正式に決定したという。このモデルは、ホンダが進める「0シリーズ」コンセプトの上級版として、従来のSUVに代わる次世代フラッグシップとなるはずだった。
しかし、日経アジアの報道によれば、ホンダは2030年までのEV関連投資額を従来の10兆円(約686億ドル)から7兆円(約480億ドル)に縮小する方針を固めた。これは単なる一車種の中止ではなく、ホンダのEV戦略全体に対する大幅な見直しの表れである。
とはいえ、今年初めに発表された0シリーズの中核モデルであるEVセダンとミッドサイズSUVについては、計画どおり2026年の投入を予定しており、完全撤退というわけではない。
また、ホンダは2030年までにEVを7車種市場に投入するとしていたが、そのうちどれが継続され、どれが削減対象となるかについては明言されていない。
この背景には、アメリカ市場におけるEV需要の鈍化がある。特にバイデン政権下で実施されたEVへの税制優遇措置がまもなく終了する可能性が高く、消費者が積極的にEVを選ぶインセンティブが低下している。
ホンダとしては、販売が読めないEVよりも、確実に需要があるハイブリッド車の開発に注力するという、実利的な判断を下したと見られる。
第2章:中国EVメーカーの圧倒的な存在感と脅威
ホンダがEV戦略を見直す要因の一つが、中国EVメーカーとの競争激化である。
BYD(比亜迪)、NIO(蔚来)、Xpeng(小鵬)といった中国系新興メーカーは、驚異的なスピードで車両開発を進め、価格競争力とテクノロジーの両面で欧米日メーカーを脅かす存在に成長した。特にBYDは、EV+PHEVの合計でテスラを抜き、世界最大の電動車メーカーとなっている。
中国政府による強力な補助金政策とサプライチェーンの内製化によって、中国勢は低価格かつ高性能なEVを大量生産できる土壌を整えており、これに対抗するのは容易ではない。
さらに2024年以降、欧州においても中国車のシェアは急増しており、フランスやドイツのメーカーは国内産業の空洞化を警戒し始めている。
ホンダとしても、アメリカでのEV販売が伸び悩み、かつ中国勢とのコスト競争が見通せない中で、大型EVに巨額投資を続けるのは「リスクが高すぎる」と判断したのは当然の帰結といえる。
第3章:欧米日メーカーのEV計画見直し──撤退・延期・縮小の連鎖
EV計画の見直しを迫られているのはホンダだけではない。2024年から2025年にかけて、複数の著名な自動車メーカーが、相次いで戦略の修正・撤回を発表している。
- ロータス:2024年11月、2028年までのフルEV化計画を撤回し、ハイブリッド開発に再注力することを発表。
- ポルシェ:2030年までに販売台数の80%をEVにするという目標は未達になると認め、今後はハイブリッド車を強化する方針にシフト。
- 日産:2025年1月、小型EV SUVの開発計画を白紙撤回。
- ミニ(BMW):ガソリンエンジン車の生産を当面継続することを表明。
- ボルボ:EV販売目標の未達成を認め、戦略の修正を進行中。
こうした動きは、EV市場の飽和や価格競争、インフラ不足、原材料コスト高騰など、多くの課題が背景にある。
第4章:再評価されるハイブリッドと内燃機関
EV市場が踊り場を迎えたことで、ハイブリッド車(HEV)やプラグインハイブリッド車(PHEV)、さらには合成燃料対応の内燃機関が、ふたたび脚光を浴びている。
- BMW:内燃機関を「技術の基盤」と位置づけ、今後もエンジン開発を継続すると明言。
- ランボルギーニ:新型V8エンジンがe-fuel(合成燃料)に対応可能であるとし、持続可能な高性能エンジンとして展開。
- メルセデス・ベンツ:EV専用プラットフォームの投入を一部延期し、既存のICE車を延命。
- アウディ:今後10年間、ガソリンエンジンを並行して販売すると発表。
つまり、各社とも「内燃機関の終焉」という過去の予測を修正し、現実に即した柔軟な戦略を取り始めているのだ。
第5章:ソニー・ホンダモビリティ(SHM)の行方──EV戦略転換の中で問われる存在意義
ホンダがEV戦略を見直す中で、忘れてはならないのがソニーとの合弁会社「ソニー・ホンダモビリティ(Sony Honda Mobility, 以下SHM)」の存在だ。
このSHMは2022年に設立され、2026年に高級電気自動車「AFEELA(アフィーラ)」の市販を目指すという大きな目標を掲げていた。車両にはソニーが得意とするエンタメ・センサー・UX(ユーザー体験)技術を融合させ、「スマートフォンの次はスマートカーだ」と意気込んでいた。
2023年のCESではそのプロトタイプが披露され、注目を集めたが、2024年以降のEV市場の停滞により、その進捗は鈍化しているように見える。
2025年現在、SHMからの明確な続報はなく、市販化の道筋は不透明だ。AFEELAのような高価格帯のスマートEVは、今まさに需要が落ち込んでいる領域であり、SHMにも再構築の圧力がかかっている。
ただし、AFEELAプロジェクトが培う技術はホンダにとっても重要な資産であり、UXやソフトウェアの知見は今後のハイブリッド車にも応用可能である。
第6章:ホンダの生き残り戦略──現実を見据えた柔軟性
ホンダは単にEVから撤退しているのではない。むしろ、市場の現実を見据えた柔軟な対応を進めているとも言える。
- ハイブリッド車のラインナップ強化
- EVは戦略的に中型以下の車種を中心に展開
- SHMやGMとの提携による技術開発の分散
将来的なEVシフトは引き続き視野に入れつつ、足元では利益確保と生産効率のバランスを取ることに注力している。
第7章:2030年に向けて──変化するモビリティの未来
2030年までのEV完全シフトという構想は、多くの企業で修正を迫られている。ホンダの方針転換は象徴的な出来事ではあるが、それは同時に「現実とのすり合わせ」に過ぎない。
- EVは万能ではない
- 市場ごとの戦略最適化が必要
- ハイブリッド、PHEV、e-fuelなど多様な道が模索されている
この変革期において、ホンダのようにフレキシブルな対応を取れる企業こそが、生き残りの鍵を握ることになるだろう。


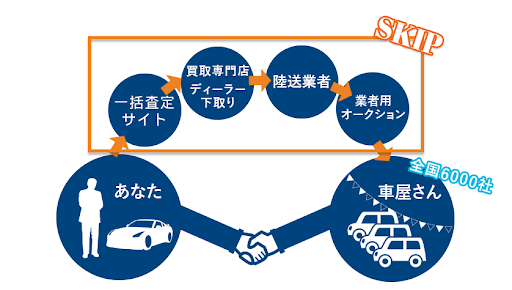

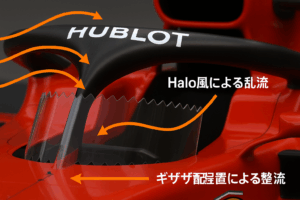






コメント