■冒頭:わずか時速4マイルオーバーで免停?


2024年12月、ロンドン南部でポルシェ・マカンを運転していたアンディ・ウィルマン氏が、自動スピードカメラにより速度違反として検挙されました。彼は『トップギア』や『グランド・ツアー』といった大ヒット自動車番組のプロデューサーとして知られ、現在は『クラークソンの農場』を手掛けている英国の有名人です。
しかしその違反内容は、「時速20マイル(約32km/h)制限の区間を24マイル(約38.6km/h)で走行した」という、たった「時速6kmオーバー」でした。それでも英国では「自動検知×免許ポイント制×収入比例罰金」という三重の交通違反処分ルールが存在し、これは彼にとって4度目の速度違反であったため、6ヶ月間の運転免許停止処分が下されたのです。
このニュースは、古いスタイルの交通取り締まりが今も横行する日本にとって、まさに「見習うべき制度」の一例です。本記事では、イギリスの制度を詳細に解説しながら、日本が参考にすべき理由を段階的に紐解いていきます。
第1章:英国の交通違反取り締まりは「自動検知」が基本
● 自動スピードカメラでの摘発が標準化
イギリスでは、速度違反の取り締まりは基本的に自動スピードカメラによって行われます。ドライバーが知らないうちに撮影され、違反通知が郵送で届く——まさに公平・客観的な取り締まり手段です。
日本では今もなお、警察官が物陰に隠れて取り締まる「ネズミ捕り」が主流ですが、これは「罠」のように感じるドライバーも多く、信頼性の点でも時代遅れと言わざるを得ません。こうした点からも、日本は自動検知の取り締まり制度を全国で導入すべきです。
● 速度違反は「1mphでもアウト」
英国の法律では、速度制限をたとえ1マイル(1.6km/h)でも超えれば違反となる可能性があります。実際の運用では「速度制限+10%+2マイル」程度までは猶予がある場合もありますが、それを超えると厳格に処罰されます。
このような明確なルールの存在こそが、交通秩序を保つ最大の武器です。日本でも「速度制限の1割超まではセーフ」といった曖昧な運用ではなく、誰にでもわかる明文化されたルール体系を導入すべきです。
第2章:免許停止はポイント制で管理、ルールは一貫して明快
● 違反のたびに「ポイント加算」、累積で免停
イギリスでは、交通違反のたびに「ポイント」が加算され、累積で一定値を超えると免許停止処分になります。
| 違反回数 | 累積ポイント | 処分内容 |
|---|---|---|
| 初回 | 3点 | 罰金のみ |
| 4回目 | 12点 | 免許停止6ヶ月 |
| 再違反 | 12点 | 免許停止12ヶ月 |
| 三度目 | 12点 | 免許停止2年間 |
このシステムは非常に分かりやすく、累積点数も明確に提示されるため、ドライバーは自分の違反歴を常に意識することができます。日本でもこのようなポイント管理を明文化し、誰もが把握できる形で導入すべきです。
第3章:罰金は「年収に比例」する仕組みが常識に
● 年収6000万円のウィルマン氏に22万円の罰金
今回のウィルマン氏のケースでは、たった4マイルオーバーにもかかわらず、約1400ドル(約22万円)の罰金が科されました。これは彼の年間所得6000万円(税引き後)に基づいて計算されたものです。
イギリスでは、Speeding Fine Calculator(速度違反罰金計算機)によって罰金額が自動で算出される仕組みになっており、「軽微な違反でも高所得者にはそれなりの負担を課す」ことにより、真の公平性が保たれています。
● 所得無視の日本の「定額制罰金」では意味がない
対して日本では、反則金はほぼ一律。たとえば、10km/h未満の速度超過で9,000円。これは年収300万円でも1億円でも変わりません。これでは高所得者にとって、違反しても何の痛手にもならず、抑止力としてはまったく機能しません。
公平な制度とは、経済状況に応じた「実効性のある罰則」であるべきです。日本でも、収入比例の罰金制度を速やかに導入すべきです。
第4章:罰することが目的ではなく、安全確保が目的
● カメラの設置場所は「公開」されている
イギリスでは、スピードカメラの設置場所はすべて政府サイトや地図上で公開されています。なぜなら、目的は違反を「見つける」ことではなく、「未然に防ぐ」ことだからです。
日本では、取り締まりポイントは隠され、むしろドライバーの不意を突くような場所に設けられるケースもあります。これでは安全確保ではなく、まるで「取り締まり件数のノルマ達成」が目的のように見えかねません。
こうした背景を考えれば、日本も取り締まりの目的を「罰すること」から「抑止すること」へと明確に転換すべきです。
第5章:AI時代の交通社会にふさわしい制度とは?
● 人の感情を排した「システム判断」が時代に合う
今後、完全自動運転やAIによる車両制御が普及していく中で、交通違反の取り締まりも「主観ではなく、データとアルゴリズムで判断される」時代になることは確実です。
その意味でも、イギリスのような「自動検知×ポイント制度×収入比例罰金」は、感情を挟まずに公正に運用できる制度として非常に優れており、日本も今のうちから導入を検討すべきです。
第6章:日本が今すぐ参考にすべき3つの制度改革案
① 自動検知カメラの全国整備と透明化
-
オービスの全国展開を進め、設置場所も公開すべき。
-
警察官による隠密的な「ネズミ捕り」から脱却すべき。
② 所得に応じた罰金制度の導入
-
確定申告や住民税からおおよその年収を把握し、罰金を収入比例で計算すべき。
-
高所得者にも「痛み」を伴わせる仕組みを導入すべき。
③ ポイント制をより明確・可視化
-
違反点数の累積状況をオンラインで確認できるようにすべき。
-
マイナポータルやスマホ通知で警告を受け取れるような仕組みも検討すべき。
結論:日本の交通取り締まり制度はアップデートが急務
かつてのように「隠れて取り締まる」「定額の罰金で済ませる」やり方では、もはや現代社会には通用しません。今求められるのは、テクノロジーと法制度の融合による「公平で効果的な交通ルール」です。
アンディ・ウィルマン氏の事例は、単なる有名人の違反ではなく、イギリスという国家が築き上げた高度な制度運用の成果です。日本が今後、真に「交通安全と公平性」を両立した社会を目指すなら、イギリスのこの仕組みを本気で参考にすべき時が来ているのです。


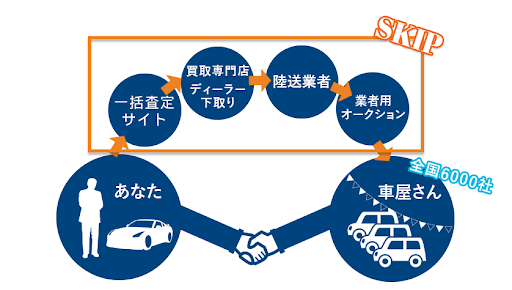








コメント