日産が迎える変革の時──追浜・平塚工場の閉鎖と米国生産移転の深層
セントラの米国生産検討から見える、日産の岐路と再生戦略


序章:変革の兆し──セントラ米国生産計画の報道
2025年5月、米Automotive Newsの報道により、日産がコンパクトセダン「セントラ(Sentra)」の生産をメキシコから米国へ移す可能性があることが明らかになった。この動きは、ドナルド・トランプ米大統領による25%の自動車関税政策を回避しつつ、北米市場での競争力を高める狙いとされている。
しかし、この報道が意味するのは単なる生産地の変更ではない。背後には、日産が今まさに直面している深刻な経営課題と、大胆な再編成の必要性が横たわっている。追浜工場と平塚工場の閉鎖計画、そして新体制下における経営方針の見直しは、その象徴的な一歩だ。
本記事では、日産の国内工場閉鎖と米国シフトの背景、そして今後のグローバル経営戦略について、徹底的に分析・考察していく。
第1章:追浜・平塚工場とは何か──その歴史と役割
1-1. 追浜工場の誕生と日本初の量産体制
日産追浜工場は1961年に設立され、同社初の近代的な大規模生産拠点として機能してきた。スカイラインやフェアレディZなど、日本車史に名を刻むモデルの製造を担い続け、「技術の日産」の代名詞ともいえる存在であった。
1-2. 平塚工場と研究拠点としての意義
一方、神奈川県平塚市に位置する平塚工場は、生産拠点というよりも研究・試作、品質評価の中核として機能。日産の先進技術の開発支援を行い、多くの次世代車両に貢献してきた。
1-3. その閉鎖が意味するもの
この2拠点の閉鎖は、日本の自動車産業が誇る高度な技術・人材・文化の喪失を意味する。単なるコスト削減では済まされない、日本の製造業にとっての象徴的な出来事である。
第2章:米国セントラ生産の背景──「関税回避」だけではない
2-1. トランプ政権の25%関税とメキシコ生産の限界
セントラは現在メキシコで生産されているが、米国の自動車輸入に対する25%の追加関税が現実味を帯びてきたことで、米国内生産へのシフトは現実的な選択肢となっている。
2-2. 北米市場での小型セダン復権とセントラの重要性
2025年第1四半期、セントラの米国販売は前年同期比36.1%増と大幅に伸長し、同社の主力SUV「ローグ」に次ぐ販売台数を記録した。2万ドル台前半の価格設定も功を奏し、「安価でまともなセダン」として再評価されている。
第3章:日産の販売動向と新経営陣の戦略
3-1. 2025年第一四半期の販売動向
-
セントラ:+36.1%
-
ヴァーサ(Versa):+156%
-
キックス(Kicks):+84.8%
これらエントリーモデルの好調が、日産全体の北米成長(+6.3%)を牽引している。これはコロナ禍以降の価格高騰により、手頃な車への需要が再燃していることの証左でもある。
3-2. 新CEOの改革──構造改革の断行
新たに就任した日産のCEOは、従来の戦略を一新。不要なプロジェクトを凍結し、工場閉鎖・人員削減を断行しつつ、次世代車の開発にリソースを集中させている。特に以下の2点が注目される。
-
次世代セントラの開発
-
テネシー州でのEVリーフとPHEVローグ生産
第4章:国内工場閉鎖が意味する「日本離れ」
4-1. 国内生産の急激な縮小
追浜・平塚の閉鎖は、単なる再編ではなく「国内生産の限界」への日産の回答とも言える。すでに村山工場や座間工場を過去に閉鎖した歴史があるが、今回は神奈川県の象徴的拠点の同時撤退であり、衝撃は大きい。
4-2. 雇用・地域経済への影響
特に追浜工場には約4,000人の従業員が在籍し、周辺の関連企業や下請けにも波及効果が及ぶと予想される。神奈川県内の産業構造にも変化が求められるだろう。
第5章:日産の将来戦略──電動化と米国偏重への転換
5-1. 北米偏重の生産体制再構築
セントラの米国生産移行、テネシー州でのEV/PHEV集中など、日産の生産体制は北米に大きくシフトしつつある。これにより、米国政策への耐性を高め、政治リスクをヘッジしようとしている。
5-2. 電動化戦略の再加速
-
新型リーフ(EV)
-
ローグのPHEV版
-
次期セントラへの電動化技術導入の可能性
これらを柱とした「実用志向のEV戦略」が再び注目されている。
第6章:グローバル市場での競争──韓国・中国との戦い
6-1. 韓国現代・起亜との価格競争
起亜フォルテやヒュンダイエラントラなど、日産セントラと競合する韓国勢は品質と価格のバランスで評価を高めており、日産が「安価な良品」ブランドとして再興するには戦略の再定義が必要だ。
6-2. 中国EV勢との電動化戦争
BYDやNIOといった中国EVメーカーは、急速な拡大と低価格攻勢で日産のグローバル競争力に圧力をかけている。とくに中国市場でのシェア後退が、日産の財務にも暗い影を落としている。
第7章:国内の今後──「技術の日産」復活への鍵
7-1. 日産技術陣の再活用
追浜や平塚で蓄積された技術や開発ノウハウを、どう継承・再利用していくか。若手エンジニアの育成と、研究部門の再編が急務となる。
7-2. 日本市場向けモデルの再定義
国内市場では、軽自動車やミニバン、PHEV SUVの需要が依然として高く、これらを中心にした商品戦略が鍵となる。
終章:日産が生き残るために──脱・過去依存の未来志向
日産は過去にとらわれず、次なる時代に即した事業構造を築く必要がある。「技術の日産」という言葉が過去の栄光で終わらぬよう、電動化・北米戦略・人材再配置という三本柱で再出発すべき時が来ている。
追浜と平塚の閉鎖は確かに喪失だが、それはまた、新たな挑戦への入り口でもある。セントラの米国生産が示すように、今こそ変革を受け入れ、日産は「再生の道」を歩み始めている。
補章:本田との合併を拒否した経営判断と役員の責任
2000年代以降、経営再建を何度も迫られてきた日産だが、そのたびに打ち出された戦略は小手先のコストカットと販売網の見直しにとどまり、抜本的な変革には至らなかった。そして特筆すべきは、ホンダとの合併提案を拒否したという重大な経営判断である。
業界内外では、この合併が実現していれば、EV開発力・グローバル販売網・ブランドイメージの全てにおいて両社が補完関係を築けたとする声が多い。にもかかわらず、保身と既得権益にしがみついた大勢の役員たちがその可能性を握り潰した事実は、今日の苦境と無関係とは言えない。
現場の従業員や地域社会に犠牲を強いる前に、まずはこうした無能な経営陣こそ削減の対象とすべきではないか。このような企業風土を変えない限り、「再生」など絵に描いた餅で終わるだろう。


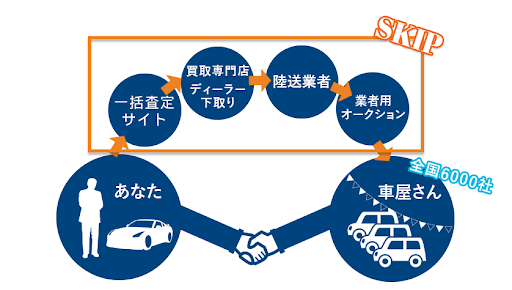








コメント