第1章:日産、2万人削減の衝撃


日産が2万人規模の人員削減を検討しているというニュースは、日本の製造業界にとって大きな衝撃となった。当初、同社は2024年末に約9,000人の人員を削減すると発表していたが、Nikkei Asiaの報道によると、その数は最終的に約2万人、つまり全世界の従業員の15%に達する可能性がある。
この発表は、2025年3月期の決算発表と時を同じくして行われるとされ、日産に対する市場の不信感がさらに強まることは間違いない。日本企業の象徴とも言える自動車メーカーが、ここまでの大規模リストラを断行せざるを得ない背景には、表面化していない深刻な経営問題が潜んでいる。
従業員数の15%という削減は、単なるコストカットでは済まされないレベルである。日産という企業そのものの「あり方」を根底から見直す必要性が浮き彫りとなった。
第2章:2024年度決算と巨額赤字の実態
日産は2024年度の業績見通しを下方修正し、最終赤字が7,000〜7,500億円に達する見込みだと発表した。売上高は12.6兆円とされるが、そこから算出される利益率は極めて低く、事実上の”焼け石に水”状態となっている。
2024年のグローバル販売台数も3.35百万台にまで下方修正された。これは世界的なEV移行、部品供給網の混乱、さらには新興国市場でのシェア低下など複合的要因が絡んでいる。
特に注目すべきは、これらの赤字の大部分が「資産の減損」と「構造改革費用」によるものである点だ。すなわち、日産自身がこれまでの経営資源の使い方を否定し、今になって“清算”し始めたということである。
第3章:新CEOイバン・エスピノーサ氏の改革路線
2024年にCEOに就任したイバン・エスピノーサ氏は、日産社内でも「改革派」として知られる人物である。彼のリーダーシップの下、日産は組織体制・資産・商品ラインナップすべての見直しを進めている。
エスピノーサ氏は声明の中で、「今後は財務基盤の安定と商品力の強化を最優先に取り組む」と語っているが、現時点では“言葉だけ”に聞こえてしまうのが実情である。特に今回の人員削減について、「関税の影響は考慮していない」と述べており、米中関係や世界経済の不確実性に対する対応力に疑問が残る。
第4章:売れているのに儲からない──米国での現状
興味深いことに、2024年の米国市場では日産の販売台数は前年同期比で5.4%増加している。しかし、この成長には大きな代償があった。それは「利益なき販売」である。
日産は「Nissan One」という新たなプログラムを導入し、ディーラーに対して販売台数に応じたキャッシュボーナスを提供している。これは、たとえ赤字で販売しても台数を稼ぐための施策であり、ブランド価値の毀損と販売網の疲弊を招くリスクが極めて高い。
売れても利益が出ない、という状況は、企業としての持続性を著しく損なう。短期的な販売数向上に目を奪われ、長期的な信頼とブランド価値を犠牲にする選択が果たして正しいのか、再考の余地がある。
第5章:なぜここまで悪化したのか──失策の連続
今回の大規模リストラの背景には、ゴーン体制崩壊後の「経営の迷走」がある。かつては世界をリードするEVとして注目されたリーフも、その後のモデル開発においてトヨタやテスラに後れを取り、アリアは価格競争力の乏しさと航続距離の中途半端さで市場に埋もれた。
アライアンス戦略も空回りしている。ルノーとの関係見直しも進まず、日産内部でも方針が統一されていない。明確な戦略の不在は、社員の士気を下げ、優秀な人材の流出を招く最大の要因となっている。
第6章:「削減」の前にやるべきこと──無責任な経営陣の刷新
社員の間では「まず無能な役員を切れ」との声が強まっている。実際、現場は過剰な業務負荷と士気低下で限界を迎えている一方、役員報酬や経営会議の姿勢に変化は見られない。
構造改革を進めるのであれば、まず「経営層からの血を流す」べきだろう。欧米企業では当たり前のこの姿勢が、日本企業では欠如している。責任の所在が曖昧なまま、従業員だけを切るという手法はもはや時代遅れだ。
グローバルでの競争力を取り戻すには、まず経営陣の刷新と責任体制の明確化が急務である。
第7章:復活の鍵は“車”にあり──製品力と開発力の強化を
かつての日産は、フェアレディZ、スカイラインGT-R、初代リーフなど、数々の革新を生み出してきた。ユーザーを魅了し、世界の自動車文化に大きな影響を与えた存在だった。
今、求められているのは“かつての輝き”の復活ではなく、未来のユーザーに刺さる製品を創造する力である。AI技術、次世代バッテリー、新しいモビリティサービスなど、未来志向の技術に本気で投資すべき時が来ている。
日産の強みは“モノづくり”にある。その本質を思い出すべきだ。
第8章:再生か衰退か──日産が日本企業に投げかける問い
日産の経営危機は、一企業の失敗ではなく、日本型経営全体の問題を象徴している。
・責任を取らない経営陣 ・決断を先送りする企業文化 ・短期的成果に頼る経営姿勢
これらの問題は、少子高齢化や国際競争力の低下に悩む他の多くの日本企業にも共通するものである。
日産が今後どのような道を歩むのかは、日本の製造業全体にとっても試金石となる。大胆な決断と、本質的な改革を断行できるかどうか──それが企業としての生死を分ける鍵である。
社員だけを犠牲にするのではなく、経営陣自らが覚悟を示すことで、初めて日産は真の意味で再生への一歩を踏み出すことができるのではないだろうか。


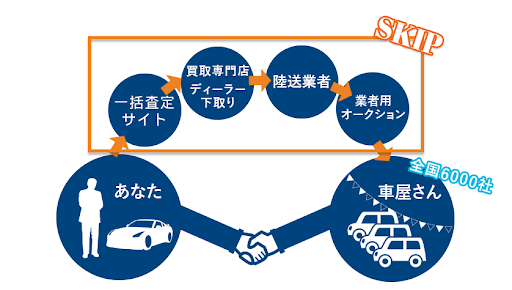








コメント