
序章:電動化の波に抗うマツダの意思
今、自動車業界は劇的な転換期を迎えている。各国の厳しい環境規制、EVシフト、カーボンニュートラルへの圧力により、多くのメーカーが内燃機関の開発を停止、あるいは縮小している。しかし、その中でマツダは真逆の道を選んだ。彼らは「理想の内燃機関」を追い求め、Skyactiv-Zという新たな挑戦を始めたのだ。
この技術は単なるエンジンの改良ではない。マツダがこれまで積み重ねてきたスカイアクティブ技術の集大成であり、次の時代へ向けた内燃機関の“最終進化形”とも言える存在だ。本稿では、Skyactiv-Zの詳細と、それに至るまでのスカイアクティブシリーズの進化の歴史、そして今後のマツダのビジョンについて深く掘り下げていく。
第1章:スカイアクティブ・テクノロジーの始まり
原点に立ち返るマツダの哲学
マツダがスカイアクティブ技術を世に出したのは2011年。エンジン、トランスミッション、ボディ、シャシーといったクルマの基本構造すべてを刷新し、効率と楽しさを両立することを目指した。
初代スカイアクティブ-Gエンジン(ガソリン)は、異常に高い14.0の圧縮比を持ち、自然吸気エンジンとしては異例の効率を達成。一方、スカイアクティブ-D(ディーゼル)は低圧縮(14.0)のコンセプトで従来の常識を覆し、軽量化とレスポンスを手に入れた。
この時期からマツダは「走る歓び」と「環境性能」の両立を掲げ、独自路線を歩み続けてきたのだ。
第2章:Skyactiv-Xという挑戦
ガソリンとディーゼルの融合、「SPCCI」技術
2019年、マツダは次の一手としてSkyactiv-Xを投入。このエンジンの最大の特徴は「SPCCI(Spark Controlled Compression Ignition)」、つまり火花点火制御圧縮着火という革新的な燃焼方式だった。
通常のガソリンエンジンのように点火プラグを使いながら、ディーゼルのような圧縮着火も実現。これにより、トルクの立ち上がりが早く、燃費もディーゼル並みという理想を掲げた。
しかし、SPCCIの技術は極めて複雑で、製品としての浸透には苦戦した。日本ではMAZDA3やCX-30などに搭載されたが、グローバルでは限定的な採用に留まった。
第3章:スカイアクティブZへの進化
“究極の内燃機関”へ
2023年11月、マツダはSkyactiv-Zの開発を発表。そして2025年3月、次世代CX-5に初搭載されることが明らかになった。
このエンジンは2.5L直列4気筒ガソリンをベースに、マツダ自社開発のハイブリッドシステムを組み合わせたもの。Euro7、LEV IV、Tier 4といった次世代排ガス規制をクリアしながら、従来のSkyactiv-G/Xよりも大幅に広い燃焼領域と高い熱効率を実現している。
マツダはこれを「SPCCIの面展開」と呼び、より幅広い運転状況でこの燃焼モードを活用できるよう改良。これにより、燃費、トルク、排ガス、どれも妥協のないパフォーマンスを狙っている。
第4章:熱効率と“λ(ラムダ)”の追求
燃焼の究極点「λ=1」を常時キープ
Skyactiv-Zのもう一つの鍵は、「空燃比制御」の最適化だ。
空燃比(ラムダ値)が1.0とは、理論的に完全燃焼が行われる状態を意味する。マツダはこの状態をより広範囲で維持するために、燃焼室内の熱分布や混合気の形成、さらには新型の断熱素材による遮熱技術まで導入している。
つまり、燃料を無駄にせず、有害物質を最小限に抑えながら、最大限のパワーを得る。そのための物理的・電子的な制御技術を、惜しみなく注ぎ込んだのがSkyactiv-Zなのである。
第5章:直6とロータリーへの波及
スカイアクティブZの知見はすべてのエンジンへ
Skyactiv-Zで得られた燃焼知見は、マツダが投入を続ける直列6気筒エンジンにも反映される。マツダは2022年以降、CX-60やCX-90などで直6ディーゼルとガソリンを展開しており、Z技術はこれらの改良に役立てられる予定だ。
さらに注目すべきは、ロータリーエンジンへの応用だ。MX-30 e-Skyactiv R-EVで復活したロータリーは、今後より大型化・高出力化され、2ローター仕様の開発も進んでいる。アイコニックSPコンセプトで披露された美しいプロポーションとともに、再び夢のロータリーが現実味を帯びている。
第6章:Skyactiv-Zがもたらす未来像
エンジンの数は半減、でも性能はアップ
マツダはSkyactiv-Zの登場により、エンジンのバリエーションを50%以上削減すると発表している。これは設計・生産の効率化と、電動化へのリソースシフトを見据えたものだ。
しかし、それは決して“妥協”ではない。むしろ、Skyactiv-Zの性能が高いため、少ない種類で多様なニーズに応えることが可能になる。しかも、従来の排ガス規制対応のために性能を30%落とす必要があったとされるところを、Zでは性能維持どころか、むしろ向上すら実現している。
第7章:エンジンと共に生きるマツダの美学
数字では語れない“魂動(こどう)”の世界
マツダは常に“人馬一体”を掲げてきた。「走る楽しさ」や「エンジン音」「加速のフィーリング」は、数値やEVのスペックでは語れない部分だ。Skyactiv-Zは、ただの効率追求ではなく、ドライバーとクルマの感性をつなぐための技術でもある。
結語:内燃機関の終焉ではなく、進化の最終章へ
電動化が加速する中、多くのメーカーがエンジンに見切りをつける中で、マツダは「まだやれることがある」と信じている。そしてそれを実現しようとする情熱がSkyactiv-Zには詰まっている。
これは単なる技術革新ではなく、“エンジンが好きだ”という純粋な想いの結晶である。
そして、私たちもそれに応えるように、Skyactiv-Z搭載車に触れ、その鼓動を感じ取っていきたい。


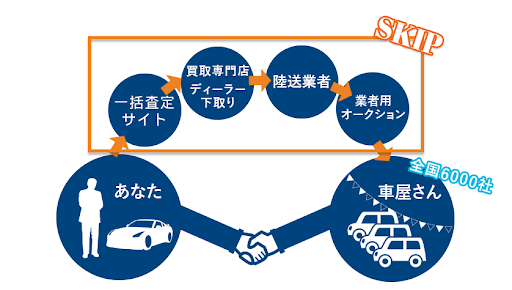







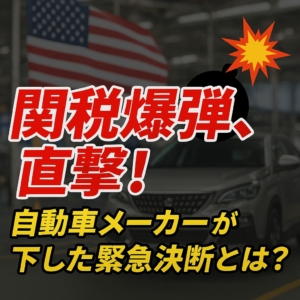
コメント