20年の沈黙を破って…2026年プレリュード、再起動!ホンダが見せた“走りの美学
「ホンダ・プレリュードが復活する」──そのニュースが初めて報じられた瞬間、全国のクルマ好きが心を震わせた。かつて青春を共にしたあのクーペが、現代に甦る。しかも、ただの懐古主義ではなく、最新のハイブリッド技術とプレミアムな内装をまとい、2026年モデルとして再誕するというのだから、期待が高まらないはずがない。
だが、なぜプレリュードなのか? シビックやアコードのように長く続いたシリーズでもなく、S2000のようなサーキット志向でもない。それでもプレリュードは、ホンダにとって、そして我々にとって、特別な意味を持っていた。時代を先取りした技術、都会的なデザイン、そして「ちょうどいい」スポーツ感。これこそが、プレリュードの真価だったのだ。


第1章:プレリュードの系譜──5世代が刻んだ“前奏曲(Prelude)”
■ 初代プレリュード(1978〜1982年)


1978年11月。ホンダが新たな試みとして送り出した2ドアスペシャルティクーペが「プレリュード」だった。その名の通り、“前奏曲”を意味するこのクルマは、シビックやアコードといった量販モデルとは一線を画す存在。シャシーはアコードをベースにしていたが、エレガントなスタイルと先進装備で、当時の若者や新しもの好きの心をつかんだ。
最大の特徴は、日本車として初めて電動サンルーフを標準装備したこと。欧州車にも通じる開放感と、どこか上品な雰囲気が魅力だった。エンジンは直4・1.8L SOHCで、運転の楽しさというよりは、都会的な洗練とスタイル重視の“走れるパーソナルカー”という立ち位置だった。
■ 2代目プレリュード(1982〜1987年)


2代目は、プレリュードの個性を一気に押し出したモデル。中でも最も衝撃的だったのは、1983年に世界初として市販車に搭載された「4WS(四輪操舵システム)」である。これにより低速時には後輪が逆位相、高速時には同位相に動き、抜群の操縦性を実現。当時の運転感覚に革命をもたらした。
デザインも大胆だった。角張ったボディにリトラクタブルライトという、80年代らしい未来的な意匠。ボンネットも低く、ワイド&ローなプロポーションが走りを予感させた。2代目の成功により、「プレリュード=先進技術の実験場」「オシャレなFFスポーツ」という地位を確立したのだ。
■ 3代目プレリュード(1987〜1991年)


1987年に登場した3代目では、さらに洗練されたデザインと走行性能が与えられた。全体的に丸みを帯びたフォルムに変化し、インテリアも高級感が増した。また、このモデルでも機械式4WSを継承し、操縦性の高さに磨きをかけている。
エンジンには2.0L DOHCやB20Aなどが搭載され、トルクと高回転の両立を実現。しかもこの時代のホンダは、エンジン開発においても世界トップクラスの実力を誇っており、「回して楽しい」「高回転でパワーが伸びる」特徴は、このプレリュードにも確実に反映されていた。
この世代から、欧州や北米市場でもプレリュードは一目置かれる存在になり、FFスポーツというジャンルの認知度を世界的に押し上げたのである。
■ 4代目プレリュード(1991〜1996年)


ホンダのVTECエンジン神話は、この4代目プレリュードで決定的なものとなった。搭載されたのは、H22A型2.2L DOHC VTECエンジン──最高出力200ps超を誇り、8000rpm近くまで軽やかに吹け上がるその回転フィールは、NAエンジンの醍醐味そのものだった。
ボディデザインは、重厚かつクリーン。サイドビューの直線美が印象的で、「大人のスポーツクーペ」としての風格を漂わせていた。もちろん、機械式から電子制御へと進化した4WSや、スタビリティの高いシャシー性能も抜群。まさに全方位に死角なしの完成度を誇っていた。
このモデルは、多くのファンから「最もプレリュードらしい」と評価されることも多く、現在でも中古市場では状態の良い個体に高値が付く。
■ 5代目プレリュード(1996〜2001年)


5代目は、時代の変化に対応しながらも、「スポーツクーペ」としての原点を忘れないモデルだった。丸みのあった先代に比べて、シャープでエッジの効いたボディへと回帰。エンジンには先代と同じH22A型が搭載され、VTECの高回転サウンドは健在だった。
しかし、販売面ではやや苦戦。90年代後半、日本ではSUVやミニバンが急速に台頭し、2ドアクーペの市場は徐々に縮小傾向にあった。また、兄弟車のインテグラや、ライバルのスカイラインクーペ、シルビアなども強力な存在だった。
2001年、5代目の生産終了とともに、プレリュードの歴史はいったん幕を閉じた。だが、それは決して“終わり”ではなかった。20年以上の時を経て、2026年モデルとして、その名前がふたたび我々の前に姿を現す──。
第2章:2026年モデルの姿──“あの頃の夢”が現代技術で甦る
■ シビックとインテグラの間に生まれた「ちょうどいい」存在
2026年のプレリュードが狙うポジションは明確だ。シビックほど「若さ一辺倒」ではなく、かといってアキュラ・インテグラほど「高級すぎない」。まさに“ちょうどいいスポーツクーペ”として、かつてのポジションに近い場所へと帰ってきた印象だ。
ボディスタイルは往年のプレリュードを彷彿とさせるロングノーズ&ショートデッキの美しい2ドアクーペ。デザイン上の目玉は、やはり流麗なサイドシルエットと、低く構えたフロントマスクだろう。近年のホンダ車に共通するシャープなヘッドライトとシンプルなグリルデザインは、未来的ながらもどこか“あの頃”の記憶を呼び起こす。
第3章:インテリアに宿る「現代的プレミアム感」
■ 「見せない」から「魅せる」へ──インテリアがついに公開
ホンダはこれまでプレリュードをショーモデルとして展示する際、徹底してガラスを黒く塗りつぶし、インテリアの詳細を隠してきた。しかし、2025年4月、LinkedInにて突如公開された写真には、右ハンドルの日本仕様と思われる実車の内装が写っていた。まさに「初めて見せた」そのコクピットは、車好きにとって垂涎ものだった。
■ シビック由来だが、アキュラの高級感
インテリアはシビックの最新モデルをベースにしながらも、ところどころにインテグラ──つまりアキュラブランドの意匠を取り入れている。例えば、シビックの特徴的なフルワイドのハニカム調エアコンベンチレーターは不採用。その代わりに、左右と中央に独立した吹き出し口を配したアキュラ流のレイアウトに変更されている。
タブレット型のインフォテインメントディスプレイや、デジタルメータークラスターは現代車としての必須装備。だが何より驚かされるのは、内装素材の質感だ。ソフトタッチのパネルやステッチ入りのパッド、メタル調加飾など、明らかに「Cセグメントの枠を超えた」質の高さを感じさせる。


第4章:「S+」ボタンが語るスポーツハイブリッドの未来
■ ギアがなくても“変速”する!?──ソフトウェアが作る走りの演出
センターコンソールには、ホンダ車でお馴染みのプッシュボタン式のギアセレクターに加え、ひときわ目立つ黒光りする「S+」ボタンが鎮座している。これは、ただのスポーツモード切り替えではない。ホンダが誇る最新のソフトウェア制御による擬似変速技術が、この小さなボタンに秘められているのだ。
プレリュードは、直列4気筒エンジンを発電専用に使い、駆動は主に電動モーターが担当する、いわゆるシリーズハイブリッド方式。エンジンが駆動軸に直結するのは、高速巡航時などごく限られた状況だけ。つまり、走行フィールは“EVに近い”のが基本。
そこで登場するのが「S+」モード。加速時に意図的にエンジントルクを落とし、擬似的な変速フィールを生み出す技術だ。ドライバーの感覚としては、まるで多段ATやDCTを操作しているような手応えを感じられる。しかも、パドルシフトでその“フェイクシフト”をコントロールできる可能性も高い。
スポーツカーにとって「音と演出」は走りの快感を左右する重要な要素。その点を熟知したホンダが、プレリュードに与えた答えがこの「S+」だった。
第5章:実用性は二の次──リアシートの宿命
■ GR86やBRZと同じ「2+2」の限界
プレリュードはあくまで2ドアクーペであり、実用性よりもスタイルと走りを優先した設計だ。公開された写真を見る限り、リアシートはほとんど“オマケ”のような存在。フロントシートを後ろまで下げれば、リアには大人の脚が入り込む余地はほぼ皆無。Cピラーも太く、視界も制限される。
とはいえ、この点に不満を言うのは野暮というものだろう。同様に2+2レイアウトを採用するトヨタGR86やスバルBRZも、リアシートは完全な“緊急用”。その代わり、プレリュードは荷室に期待が持てる。ベースとなったシビックは15立方フィート(約420L)ものトランク容量を誇り、ハイブリッドであっても荷室のスペース効率が極めて高い。デザインと使い勝手の両立こそ、ホンダが得意とするパッケージング技術なのだ。
第6章:ライバルたちとの比較──このプレリュードは誰と戦うのか?
2026年のプレリュードは、ユニークな立ち位置にある。FFハイブリッドの2ドアクーペというだけで、既に競合が限られてくる。あえてライバルを挙げるなら、以下の3モデルだろう。
-
トヨタGR86/スバルBRZ:軽量FR、NAエンジン+MTの楽しさでは敵わないが、質感や燃費、日常性能ではプレリュードに軍配が上がる。
-
トヨタC-HR GR SPORTハイブリッド:価格帯・HV・スタイリッシュさでは重なるが、SUV形状のため走行感覚はまるで違う。
-
マツダMX-5(ロードスター):走りのピュアさでは敵わないが、2ドアクーペとしての使い勝手や質感で優位。
つまりプレリュードは、「走りも楽しみたいけれど、実用性や快適性も捨てたくない」という現代の大人スポーツ層に向けた、まさに“中庸の美学”を体現したクルマなのである。
第7章:なぜ今、プレリュードなのか?
■ 若者にも、かつての若者にも刺さる“ホンダの美学”
現代は、クルマに対する価値観が二極化している。趣味性を追求したガチなスポーツカーと、利便性を優先したミニバンやSUV。その中間にあるべきクーペ市場は、ここ10年で急激に縮小してしまった。だが、そこに一石を投じるのがこのプレリュードだ。
しかも、Z世代の若者には「新しいクールな2ドア」として、かつてのプレリュード世代には「忘れられなかった青春の象徴」として、まったく異なる視点から同時にアピールできる希有な存在。それがこのクルマの最大の武器といえる。
第8章:今後の展望──タイプRの可能性も?
プレリュードの市販モデルは2025年末から2026年初頭にかけて発表される見込み。価格はシビックe:HEVより高く、インテグラ並みの300万円後半〜400万円台と予想されている。
気になるのは今後の派生モデルだ。例えば、**「プレリュード・タイプR」**のような走りに特化したグレードが用意されれば、Zやフェアレディ、GRカローラのようなスポーツカー勢にも肉薄できるポテンシャルを持っている。
【まとめ】──プレリュードは再び、心を動かす存在になれるか?
2026年、プレリュードは単なる復刻ではなく、“現代に合わせて進化した再解釈”として蘇る。かつての美学を受け継ぎつつ、ハイブリッドという新たな武器を手に入れたこのクーペは、ホンダが「走りの喜び」と「日常性」をどう両立させようとしているか、その答えの一つと言えるだろう。


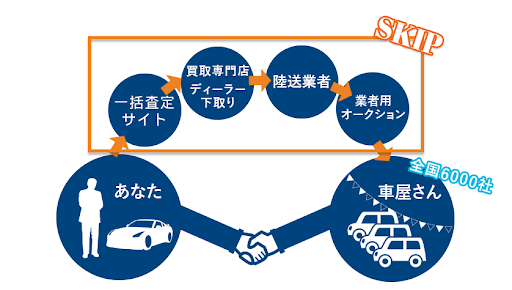








コメント