ガソリンエンジンが輝いていたころ ── 革新的なターボシステムを振り返る
2025年、世界の自動車産業は大きな転換期を迎えています。環境規制の強化と電動化の波により、多くの自動車メーカーがEV(電気自動車)やハイブリッド車への移行を進め、ガソリンエンジンは過去のものとして扱われつつあります。しかし、我々クルマ好きにとって、内燃機関の魅力は簡単に忘れ去ることなどできません。
特に、「ターボチャージャー」という技術は、ガソリンエンジンの性能を飛躍的に引き上げ、数々の名車を生み出してきました。本記事では、過去20年間で特に革新的だった10のターボシステムを振り返りながら、ガソリンエンジンの輝きと技術の進化を深く掘り下げていきます。
第1章:三菱が起こした革命 ── 2004年 ランサーエボリューションVIIIのツインスクロールターボ


2000年代初頭、日本車の中で最も注目を浴びていたスポーツセダンの一つが、三菱ランサーエボリューション。第8世代となるエボVIIIでは、ターボ技術に大きな進化が見られました。それが「ツインスクロールターボ」の採用です。
この技術は、排気流を2つに分けてタービンに導くことで、排気干渉を最小限に抑え、ターボラグを大幅に低減。さらに、低回転からのトルクを大幅に向上させ、まるで大排気量NAのようなレスポンスを実現しました。
エボVIIIに搭載された4G63エンジンは、2.0リッター直列4気筒ながら276馬力を発生。これにAWDシステムが組み合わさることで、0-100km/h加速はわずか4.5秒。WRCで培った技術と共に、市販車としても最先端の存在となったのです。
第2章:BMWの挑戦 ── 2006年 335iとツインターボの革新


続いて紹介するのは、ドイツの名門BMWが放った一撃。E90型335iには、BMW初のターボ付き直列6気筒「N54」エンジンが搭載されました。このエンジンは、ツインターボながらコンパクトで短い排気マニホールドを用いることで、驚異的なレスポンスを実現しました。
最大トルクは1,400rpmという超低回転域で発生し、従来のターボ車にありがちな「待ち時間」を感じさせませんでした。BMWはその後、N55、B58といったエンジンでツインスクロール化を進め、さらに効率とパフォーマンスを追求していきますが、すべてはこのN54の成功があったからこそです。
第3章:ポルシェの変革 ── 2007年 911ターボと可変ジオメトリー技術(VGT)


ポルシェは、911ターボを通して常にターボ技術の最先端を走ってきました。その中でも、997型911ターボに初搭載された「VGT(可変ジオメトリーターボ)」は画期的な技術でした。
このターボは、エンジン回転数に応じてタービンの羽の角度を可変させることで、低回転でも高回転でも高効率な過給が可能に。その結果、ターボラグをほぼ解消し、常にリニアな加速をドライバーに提供します。
911ターボは4WDとの組み合わせにより、0-100km/h加速3.9秒という当時としては驚異的な数値を達成。まさにターボの未来を切り開いた一台といえます。
第4章:ディーゼルの先進性 ── 2007年 ダッジRAM 3500のVGT採用


可変ジオメトリーターボの技術は、実はディーゼル車の方が先に実用化しています。アメリカのピックアップトラック、ダッジRAM 3500に搭載された6.7L直列6気筒ディーゼルには、ホルセット製VGTが組み込まれていました。
ディーゼルエンジンは排気温度が低いため、VGTのような精密なターボ機構でも耐久性が確保しやすく、実用化が早かったのです。この技術の応用が、後のガソリンターボ車へとつながっていきました。
第5章:ホットV革命 ── 2011年 BMW M5のS63エンジン


BMWは再び、F10型M5でターボ技術に挑みます。搭載されたS63エンジンは、V型8気筒のバンク内にターボチャージャーを配置する「ホットV」構造を採用。これにより、排気経路が極端に短くなり、過給のレスポンスが飛躍的に向上しました。
さらに、このホットV構造とツインスクロールターボを組み合わせたことで、かつてないスムーズさとパワーを両立。553馬力、502 lb-ftのトルクというスペックを誇りながら、日常域での扱いやすさも確保した完成度の高いパワートレインでした。
第6章:圧縮空気で即応性アップ ── 2016年 ボルボXC90のPowerPulse


北欧の革新者・ボルボは、ターボラグ解消のために全く異なるアプローチをとります。それが「PowerPulse(パワーパルス)」技術です。
このシステムは、圧縮空気タンクからタービンへ直接空気を吹き付け、スプールアップ(加速)を瞬時に行うというもの。アクセル操作と連動して空気が「パルス」され、ターボが即座に回転を開始。画期的でありながら、意外にも他メーカーには採用されていない孤高の技術です。
第7章:大衆車の革新 ── 2017年 フォルクスワーゲン ゴルフGTIのEA888エンジン


VWの名機EA888は、世界中の大衆車に搭載される中で進化を続け、第3世代ではターボマニホールドをシリンダーヘッド一体型とする大胆な設計を採用しました。
これにより排気経路が短縮され、ターボレスポンスが向上。さらに冷却効率の改善により、燃費性能も20%近く改善されました。スポーツカーだけでなく、普段使いのハッチバックでもターボの恩恵が最大限に活かされる時代の到来です。
第8章:電動で加速する未来 ── 2019年 メルセデスAMG E53のeターボ


AMGが導入した48Vマイルドハイブリッド技術は、電動補助によるターボの加速という新境地を開きました。E53では、ターボのコンプレッサーホイールに直結するモーターを搭載し、排気ガスが来る前からタービンを回すことが可能に。
その結果、従来のターボでは考えられなかった「アクセルを踏む前に過給が始まる」世界が実現。ターボと電気の融合は、新たな時代の幕開けを感じさせました。
第9章:フェラーリの矜持 ── 2022年 296 GTBとV6ハイブリッド


フェラーリといえば自然吸気V8やV12のイメージが強い中、あえてV6ツインターボ+ハイブリッドという構成を選んだのが296 GTB。その理由は、120度のVバンクという特異なレイアウトにあります。
このレイアウトによりターボの配置が最適化され、レスポンスと空力が両立。さらにリアアクスルに電動モーターを配置することで、ターボの欠点を完全に打ち消しました。819馬力という出力を誇りながら、ドライバーとの一体感を損なわない設計に、フェラーリの哲学が凝縮されています。
第10章:ターボの終着点 ── 2025年 ポルシェ911 GTSのウェイストゲートレスeターボ


そして最後に紹介するのは、ポルシェ911の最新世代GTS。このモデルには、これまでのターボシステムの常識を覆す「ウェイストゲートレス電動ターボ」が採用されています。
従来、余分な排気圧を逃がす役割を持っていたウェイストゲートですが、このシステムではそれすら不要。排気エネルギーをすべて再利用し、発電やモーターの補助に活かすという「廃棄ゼロ設計」です。加えて8速DCTに統合されたハイブリッドモーターにより、ガソリンエンジンの最高峰とも呼べるレスポンスと効率を実現しました。
結びに ── ターボ技術が教えてくれた未来
こうして振り返ってみると、ターボ技術は単なる過給装置ではなく、エンジンの未来を切り開く重要な存在だったことがわかります。低回転からのトルク、燃費向上、排出ガスの削減──そのすべてを追求した結果として、ここまでの進化がありました。
たとえ今後、ガソリンエンジンが姿を消すことになったとしても、私たちがターボという技術から学んだ熱意と創意工夫は、きっとEVや次世代パワートレインの中にも生き続けることでしょう。
ターボ、それは内燃機関の最後の輝きであり、エンジニアたちの夢の結晶だったのです。


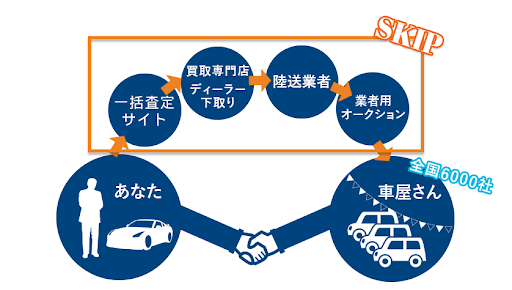

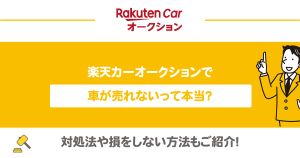

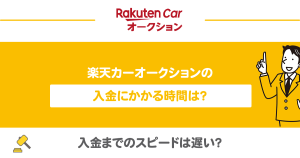
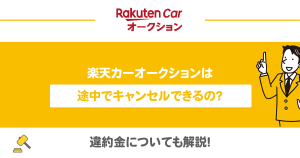
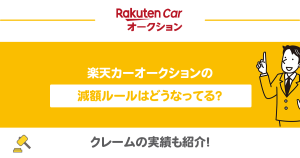
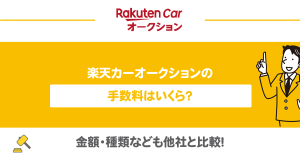
コメント